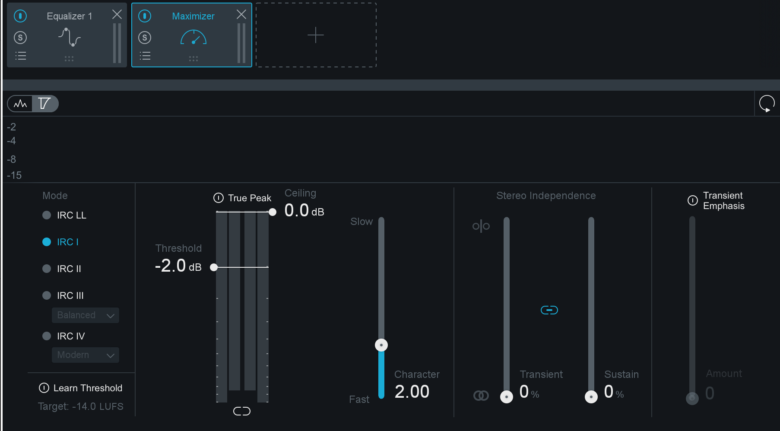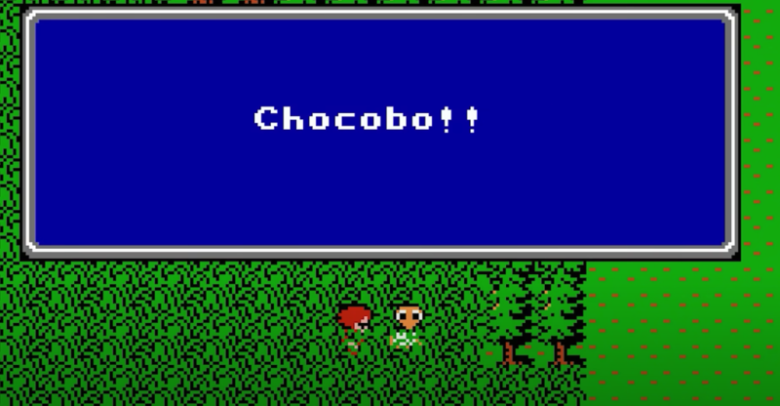昔のドラムってどんな感じだったんだろう?
このような疑問にお答えする内容です。
今回はPart3として、ドラムにとって非常に重要となる1909年の歴史を振り返ります。
Part1:ドラムの歴史のはじまり(1865年ごろ)
Part2:ラグタイムの時代
Part3:ドラムペダルの進化
Part4:ドラムブラシの誕生
Part5:ジャズとフィルインのはじまり
Part6:フィルインとシカゴスタイルのドラム
Part7:フォリーとシアタードラマー
Part8:ビッグバンドの時代
Part9:Gene Krupaと「Sing Sing Sing」
Part10:ビーバップとライドシンバル
Part11:リズム&ブルース・シャッフル・バックビート
Part12:ツーバス・ダブルバスドラムの誕生
Part13:ロカビリーのはじまり
Part14:ロックンロールのはじまり
Part15:ビートルズとマッチドグリップの誕生
1909年に起こったこととは?
1909年は、Ludwigがバスドラム用ペダルの特許を取得した年です。
実は、その前にもバスドラム用ペダルは存在していました。
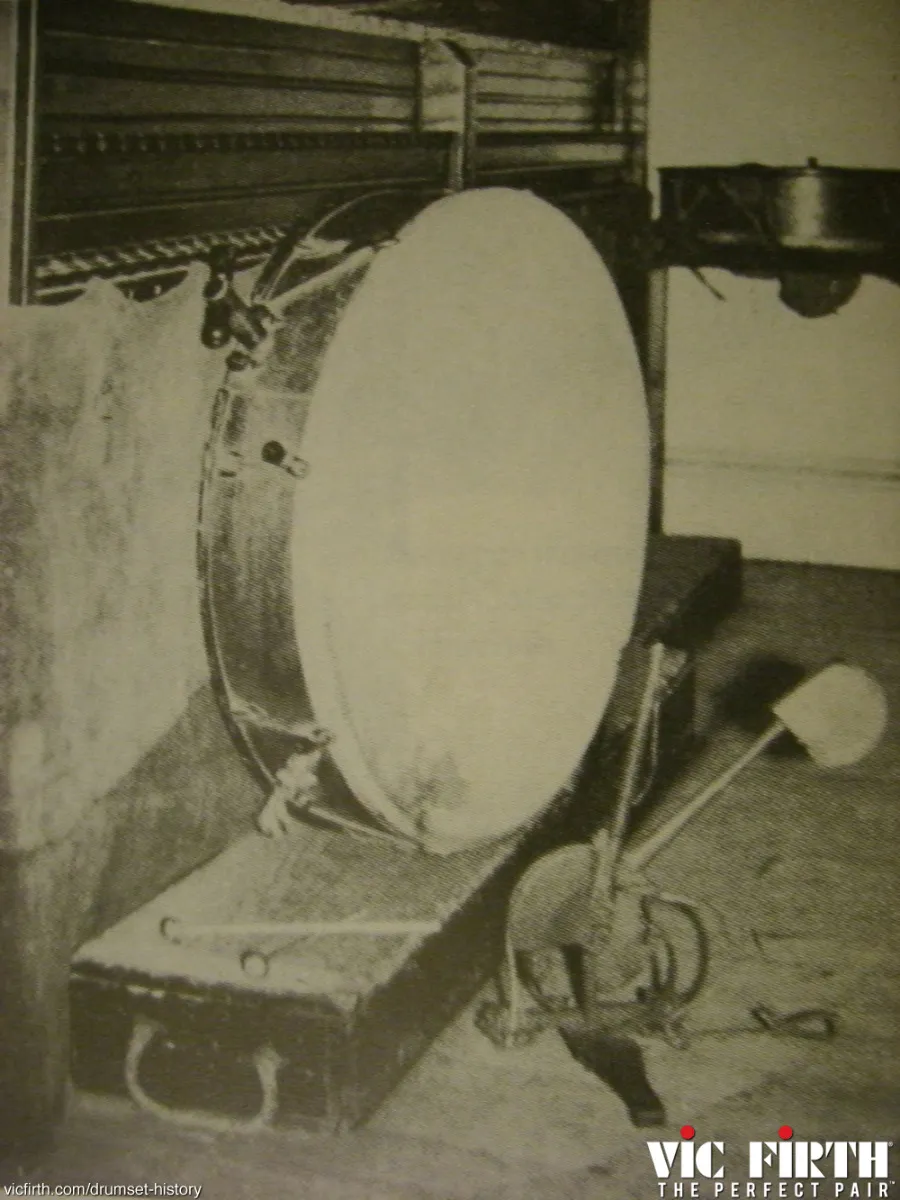
画像:昔のバスドラム用ペダル(https://ae.vicfirth.com/wp-content/uploads/03-1.webp)
1870年ごろにドラマー達は、「オーバーハングペダル」と呼ばれる、バスドラムの上に取り付けるペダルを使っていました。
しかしこのオーバーハングペダルは見た目が格好悪く、コントロールもしづらいものでした。
そのため、1870年ごろのドラマー達はダブルドラミングにはペダルを使わない方を好んでいました。

画像:Ludwigによる初期のペダル(https://ae.vicfirth.com/wp-content/uploads/03-2.webp)
今からおよそ100年前ごろに作られたLudwigのペダルは、今わたしたちが使っているペダルと非常にそっくりです。
フットボードとスプリングがあり、バスドラムに取り付けるしくみです。
100年以上も前に作られたと考えると、よく考えられて作られたものだということがわかります。
バターに付属している器具

画像:https://ae.vicfirth.com/wp-content/uploads/03-4.webp
当時のペダルには、バターヘッドに金属の器具が付いていました(上記画像、右側に飛び出ている金属の球体)。
これは、フットペダルを踏むと、バターヘッドについている器具が、バスドラムについているシンバルに当たり「カーン」と鳴るしくみになっています。

画像:ドラムペダルと、バスドラムのすぐ右横についているシンバル(https://morenomaugliani.com/wp-content/uploads/2022/11/DrumSet-1-1-1000x667.png)
ビーターのヘッド
もう一つ今の時代のペダルと異なるのは、ビーターのヘッド部分です。
実は、当時のビーターは今よりもっと大きかったのです。
これは、昔はバスドラムが非常に大きかったためです。
26,28,30インチのバスドラムが主流で、中には40インチの製品もありました。
ビーターは、マーチングバンドのバスドラムで使われていたビーター(マレット)と非常に似たものでした。
持ち運びも便利
当時の人々はまだ車を持っていませんので、交通機関を使ってドラムを運び出す必要がありました。
Ludwigが作ったペダルは、今使われているものと同様、分解することができます。
分解すればスーツの内ポケットにも収まるサイズになりますので、当時の人々にとっては非常に便利なものでした。
つづきのPart4はコチラ