昔のドラムってどんな感じだったんだろう?
このような疑問にお答えする内容です。
今回はPart9として、ドラムが一気に脚光を浴びるようになった時代を振り返ります。
Part1:ドラムの歴史のはじまり(1865年ごろ)
Part2:ラグタイムの時代
Part3:ドラムペダルの進化
Part4:ドラムブラシの誕生
Part5:ジャズとフィルインのはじまり
Part6:フィルインとシカゴスタイルのドラム
Part7:フォリーとシアタードラマー
Part8:ビッグバンドの時代
Part9:Gene Krupaと「Sing Sing Sing」
Part10:ビーバップとライドシンバル
Part11:リズム&ブルース・シャッフル・バックビート
Part12:ツーバス・ダブルバスドラムの誕生
Part13:ロカビリーのはじまり
Part14:ロックンロールのはじまり
Part15:ビートルズとマッチドグリップの誕生
1930年代とGene Krupaの活躍
1930年代「ビッグバンド時代」において欠かせないのが、ドラマーのGene Krupaの存在です。
Gene Krupaという名前は聞いたことがある人もいるかもしれません。
彼はドラムの歴史において非常に重要であり、彼なしでドラムを語ることはできません。
特に、現代の「ドラムソロ」があるのは、彼のおかげなのです。
Gene Krupaと”Sing Sing Sing”
Gene Krupaは、ドラムにおける「真のスター」といえるでしょう。
バンドの後ろで演奏しているリズムキーパー役だけでしかなかったドラムを、より前で目立たせ、ドラムを他の楽器と同じ立ち位置に立たせたのです。
これ以前の時代のタムは「ドラムに付属している中国の楽器」という立ち位置でしたが、タムは1つだけ使うのが一般的でした。
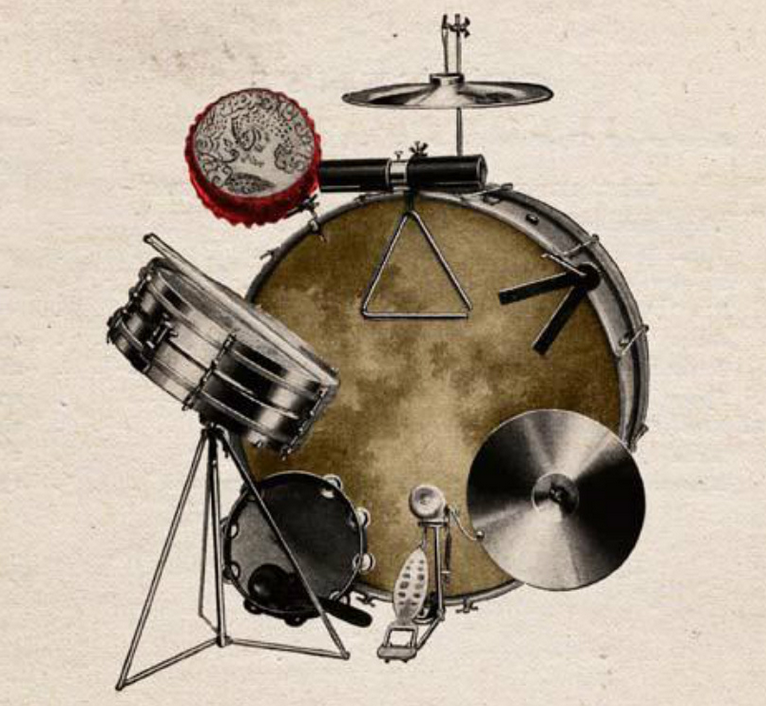
初期のドラムセット:https://morenomaugliani.com/wp-content/uploads/2022/11/DrumSet-.png
その中でKrupaが行ったのは、「違う音程にチューニングされたタムを使う」ということです。
現代では当たり前ですが、実はこれ以前はポピュラーなやり方ではなかったのです。
1935年は、みなさんも一度は聞いたことのあるあの名曲「Sing Sing Sing」が誕生した年です。
この曲でKrupaが違うピッチ・大きさのタムを使ったことで、この手法が他のドラマーにも広がりました。
この時代には他にもたくさんの人気ドラマーが名を挙げた年ですが、どのドラマーも、Krupaのようにドラムセットで自分のパーソナリティを表現するようになりました。
こうして、ドラマーがドラムソロをする文化が生まれたのです。
Gene Krupaのドラミング
つづきのPart10はコチラ










