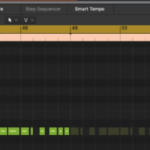今回はこのような疑問にお答えする内容です。
こちらの動画で実際の曲を聞いてみると、さらに理解を深めることができます。
「8ルール」とは?

8ルールとは、「楽曲を8小節単位で区切ること」です。
例えばAメロを8小節、Bメロを8小節、サビを8小節x2にする...などです。
「それならもうやってるよ」という方もいるかもしれません。
しかし今回は、ただ8小節に区切るだけでなく、楽曲制作全体で使えるテクニックもご紹介します。
8小節ずつ、ほんのすこし変化を加える

たとえば、最初の8小節がイントロの場合、その8小節にそのまま変化を加わえてVerse(Aメロ)にします。
このとき、ほとんどのパートに変化は付けませんが、ほんの少しだけ違いを加えてみましょう。
例えば、細かいパーカッションのループ音源を入れてみたりしてみます。
このような小さな変化を厳密に聞き取れるリスナーは少ないかもしれません。
しかし多くのリスナーは、この変化を「感じる」ことができます。
言葉で説明できなくても、「ここからAメロが始まった」と感じる要素はあります。
変化は「シンプル」でいい

8小節単位で変化を加えたいときは、シンプルな方法でOKです。
たとえば一瞬だけ無音にしてみたり、新しい楽器を1つだけ加えたり、元の音のアタック音を少しだけ強調してみるなど…
それだけでも、十分変化をつけることができます。
これは、リスナーやクライアントにダイナミックな体験を与えられる、非常に優れた方法なのです。
8ルールを「合体」させてみる

それでは、8ルールを「合体」させてみましょう。
まずは楽曲構成のアレンジから。
Verse(Aメロ)・Pre Chorus(Bメロ)・Chorus(サビ)・Break Down(静かになる部分)・Drop(ドロップ)などを8小節ごとに分け、つなげます。
次はサウンドデザインです。
ハイハットを付け足したり、サウンドは変えてメロディーはそのままにしたり、そのセクション独自のサウンドを加えてみたりしてみます。
最後はミキシング(MIX)です。
セクションによってEQの設定を変えたり、リバーブやディレイを増やしたり、他のエフェクトを加えたりします。
足し算と引き算を使い分けよう

Music notebook with wooden pencil
もちろん、これらは付け足す=足し算するだけでなく、引き算してみてもOKです。
たとえば、特定の楽器を抜いた状態で始めてみたり、ローパスフィルターをかけた状態で始めてみたり…
楽曲の盛り上がり具合に沿って、ローパスフィルターとハイパスフィルターを使い分けてみるのもいいでしょう。
楽曲構成をおもしろくさせる作曲のコツ「8ルール」まとめ
・サウンドデザイン
・ミキシング(MIX)
それぞれの段階で8ルールを使うことで、よりエキサイティングな楽曲に仕上げられます。
これさえやっておけば、つまらない曲になることはないでしょう!
ぜひおためしください。
実は「9つのルール」も...
今回は「8ルール」をご紹介しましたが、こちらの書籍では一発で記憶に残る曲を作るための「9つのルール」を解説しています。
作曲の技術を高めたい方は、ぜひご覧ください。
当サイトでは他にも楽曲構成やメロディー作りに関するテクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓