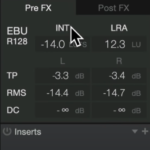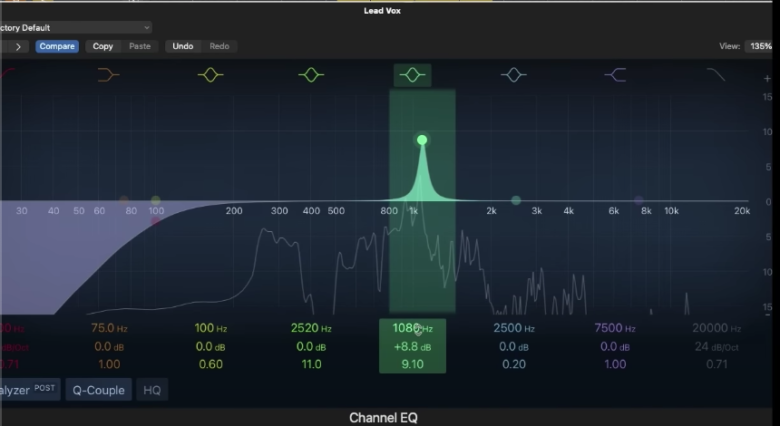マスタリングってどうやるの?
マスタリングしなきゃいけないけど、マスタリングエンジニアほど厳密にできる自信がないな…
今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。
DTMerおなじみ、数々のプラグインを販売しているiZotopeが教える「マスタリングエンジニアでない人のためのマスタリングの仕方」をまとめました。
今回はPart9として「エクスポート・書き出しの仕方」について解説します。
マスタリングエンジニアでない人のためのマスタリング講座シリーズ
マスタリングのコツ9:エクスポート(書き出し)を正しく行う

よく音を整えられたら、次はいよいよエクスポート(書き出し)の作業です。
ここで考えるべきなのは「目的」です。
どこに配信されるかによって、書き出しのフォーマットが異なります。
たとえば曲がCDで販売されるorオンラインで配信される場合は、44.1kHz、16bitのwavファイルで書き出しましょう。
また、ハイレゾ音源で配信したい場合は24bitで書き出しをする必要があります。
iZotope社の「Ozone」を使うと、音源の用途・目的に合わせて書き出しをするのが楽になりますので、マスタリングにはとてもおすすめです。
初心者の方には「Elements」、中級者の方には「Standard」、上級者の方には「Advanced」がおすすめです。

ストリーミングサービスのマスタリングはもう一工夫必要
ストリーミングサービスの場合は、マスタリングで注意するべき項目があります。
こちらについては以下の記事で解説しています。
以上で「マスタリングエンジニアでない人のためのマスタリング講座」はすべて終了です。
ここまでをマスターしたあなたなら、たとえマスタリングエンジニアでなくてもマスタリングの流れ全体を理解し、自分でラフマスタリングができるレベルに到達しているでしょう。
マスタリングの流れを理解することで、よりよいミキシングをすることにもつながりますので、音楽制作全体のレベルもアップしているはずです。
ぜひ今後の音楽制作に活かしてみてください!
当サイトでは他にもマスタリングについての解説をまとめていますので、より深く学びたい方はぜひこちらもご覧ください↓
マスタリングエンジニアでない人のためのマスタリング講座シリーズ