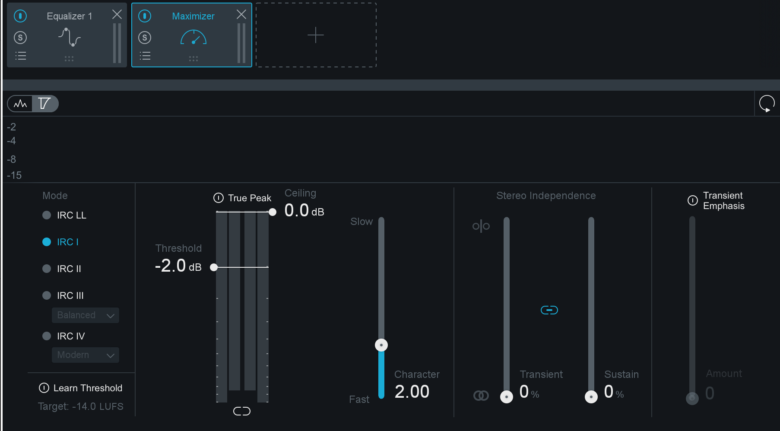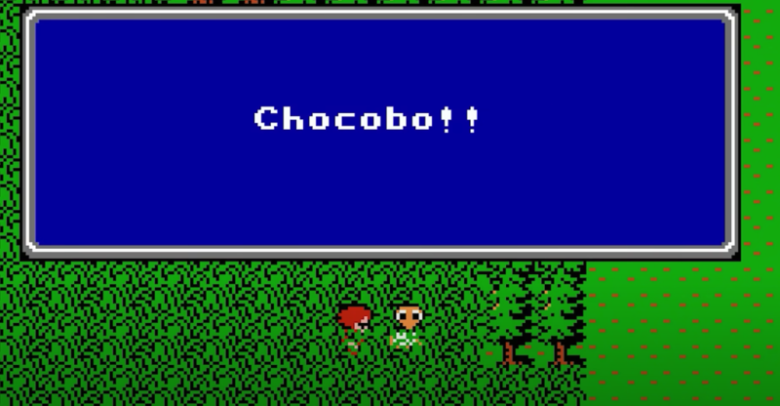今回は、このような方におすすめの内容です。
テイラー・スウィフトのアルバム「1989」の分析結果をもとに、Findeisen氏が彼女の作曲テクニックを解説。
今日から誰でも使えるテクニックばかりですので、ぜひ最後までご覧ください!
テイラー・スウィフトの曲の3つの特徴とは?
彼女の曲には、これら3つの特徴があります。
・ルート音の多用
・ほんの少しのアレンジ
それでは1つずつ解説していきます。
テイラー・スウィフトの楽曲の特徴1:ワンノートメロディー

「1989」では、ワンノートメロディーが非常に多く使われています。
ワンノートメロディーとは、その名の通り1つの音程を連続で使う手法です。
音程は同じなので、違うのはリズムと歌詞だけ、ということになります。
ここで、具体的な例を見てみましょう。
「Blank Space」Aメロ
1つ目の例は、「Blank Space」Aメロの最初。
ここではF(ファ)の音が連続で使われています。
歌詞で言うと、たとえば以下の部分です。
「Magic, madness, heaven sin」
「Welcome To New York」Aメロ・サビ
2つ目の例は、「Welcome to New York」のAメロ部分とサビの部分。
歌詞で言うと、
Aメロはこの部分↓
Kaleidoscope of loud heartbeats under coats
サビは、印象的な「Welcome To New York~」の部分になります。
「One Of The Woods」のサビ
3つ目の例は、「One of The Woods」のサビ部分で、かなりわかりやすい例です。
1:00~
「1989」でワンノートメロディは何回使われている?
分析の結果、「1989」では230回以上も使われていることがわかりました。
また、少なくとも1曲につき1回は使われていることも判明。
このワンノートメロディーは、曲作りで大きな要素と言えます。
「ワンノートメロディーは退屈」はウソ
作曲をしている方なら、教則本などに「ピアノで弾いてよく聞こえない曲は、バンドでやってもよく聞こえない」と書かれているのを目にしたことがあると思います。
しかし、このアルバムはその理論が働かないを証明しています。
ワンノートメロディーは、ピアノで弾くとつまらないメロディーに聞こえます。
しかし、テイラー・スウィフトの曲ではアレンジによっておもしろいメロディーへ変身しています。
「ワンノートメロディーはピアノで弾くと退屈だから避けるべき」というのはウソになります。
テイラー・スウィフトの楽曲の特徴2:ルート音を使う

ワンノートメロディーは同じ音を連続で使うことを指すと先ほどご説明しました。
実は、ここで2つ目の重要なポイントが利用されています。「ルート音を使う」です。
感情的な側面で言うと、ルート音は中立的です。
3rdのように感情的な響きでもなければ、5thのように冷たさを感じる響きでもなく、非常にあいまいな響きなのです。
「ファインディング・ニモ」「トイストーリー」などでおなじみの映像作家Andrew Stantonは、これを「2+2理論」と呼んでいます。
つまり、「4を与えるのではなく、2+2を与えろ」ということです。
テイラー・スウィフトの楽曲の特徴3:ほんの少しのアレンジ

アルバム「1989」を聞くと、アレンジがほんの少ししか行われていないことがわかります。
どの楽器も、絶対に楽曲から外してはならないものばかり。
もしそのパートをなくしてしまったら、曲が崩壊してしまうでしょう。
すべての楽曲には場所(スペース)があり、また沈黙の部分もあります。
テイラー・スウィフトの作曲方法まとめ
テイラー・スウィフトの楽曲の特徴は「ワンノートメロディー」「ルート音を多用」「わずかなアレンジ」の3つでした。
これらを3つ使えば、彼女のように耳に残りやすい、素晴らしい楽曲やメロディーを作ることができるでしょう。
今回ご紹介した「1989」はもちろん、他のアルバムも自分なりに分析してみることをおすすめします。
また新たな特徴を見つけることができ、ヒット曲を作るテクニックが身につきます。
以上で解説は終了です。
当サイトでは他にも有名なアーティストにフォーカスした作曲テクニックを多数ご紹介していますので、ぜひご覧ください。
イントロ・Aメロ・Bメロ・サビ・ポストコーラス・Cメロ・アウトロの作り方は当サイトのnoteアカウントで詳しく解説しています。
各セクションの作り方がわからない方、アイデアの幅を増やしたい方はぜひこちらもご覧ください↓