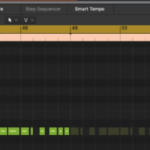世界のトップアーティストであるテイラー・スウィフトとThe Weeknd。
以前の記事「The Weekndっぽいメロディーの作り方」では、The Weekndとテイラー・スウィフトのメロディーの比較をしました。
この記事ではそれぞれのアーティストにおける3つの特徴がわかりましたが、実はもっと面白い特徴があります!
今回は、Holistic Songwritingが解説する「The Weekndとテイラー・スウィフトのメロディーの作り方の違い」を3つの要素に分けてご紹介します。
前回の記事をご覧になった前提でお話をしますので、まだチェックしていない方はまずこちらをご覧ください↓
The Weekndとテイラー・スウィフトのメロディーの違い ~3つの要素~

The Weekndとテイラー・スウィフトを比較すると、こちらの3つの要素に大きな違いがあることがわかります。
- 歌いやすさ
- メロディーの跳躍のしかた
- リズムタイプ
これらを1つずつ解説していきます。
1.メロディーの歌いやすさの違い

The Weekndはペンタトニックスケールを使っているので、音と音の間が空き、歌いにくい部分が発生します。
対して、テイラー・スウィフトのメロディーの作り方はアイオニアンを使っていることが多いので、メロディーが非常に覚えやすく、歌いやすいです。
アイオニアン(モード): 元のスケールb(フラット)が1つもないスケール。
Cメジャーアイオニアンなら「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」
Dメジャーアイオニアンなら「レ・ミ・#ファ・ソ・ラ・シ・#ド」
加えて、前回ご紹介した通り、テイラーはワンノートメロディーを多用しています。
(アルバム「1989」においては、ワンノートメロディーが230回以上使われています)
そのため、テイラーの楽曲の方が歌いやすいのです。
2.メロディーの跳躍のしかたの違い

The Weekndとテイラー・スウィフトのメロディーの作り方は、メロディーが跳躍するとき、ルート音から1オクターブ上のルート音に飛ぶパターンが多いです。
対してThe Weekndは、マイナーペンタトニックスケールにもあるマイナー7thの音に飛ぶ場合が多いです。
たとえばCマイナースケールの場合。
The Weekndはドからbシに飛びます。
テイラー・スウィフトはドから1オクターブ上のドに飛びます。
実際やってみるとわかりますが、テイラーのようにルート音から1オクターブ上の音の方が音を当てやすいです。
3.メロディーのリズムタイプの違い
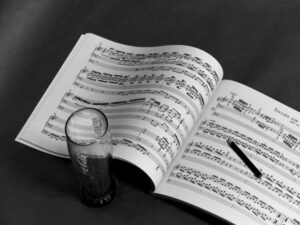
The Weekndは、3連符や短く細かい音を多く使っています。
おもしろいのは、これによりバックで流れている音と間にコントラストが生まれることです。
たとえば、Aメロでゆったりとした、ベース音が際立つディープなサウンドが流れているとします。
多くのアーティストは、メロディーもゆったりと、落ち着いた感じに仕上げます。
しかし、The Weekndは非常にリズミカルなメロディーをここに持ってくるのです。
例えばヒット曲「Blinding Lights」のメロディーでは、バックでは「ジャーン」「ドーン」というゆったり重いシンセサイザーとシンプルなドラムを中心に鳴っていますが、メロディー比較的細かい音が並んでいます。
その後はファンキーなサウンドに切り替えたりと、ここでもバッキングトラックとメロディーのコントラストが見受けられます。
これもThe Weekndのメロディー作りの特徴の1つと言えます。
テイラー・スウィフトとThe Weekndのメロディーの違いまとめ

テイラー・スウィフトとThe Weekndのメロディーを比較して、「歌いやすさ」「メロディーの跳躍のしかた」「リズムタイプ」の違いがわかりました。
これらを意識すれば、彼らのようなメロディーを作ることができます!
ぜひおためしください。
さらにメロディー作りを上達させるためには?
また、今回は「アイオニアンモード」など、モードのお話が出てきました。
作曲では非常に活躍する知識になるので、よりオリジナリティのあるメロディーを作りたい方はぜひご覧ください。
また、いいメロディーを作るには楽曲の構成を理解していることが非常に重要です。
こちらについては下記の記事で徹底解説していますので、ぜひ参考にしてください🔻
その他、当サイトでご紹介しているメロディーづくりの解説はこちら🔻