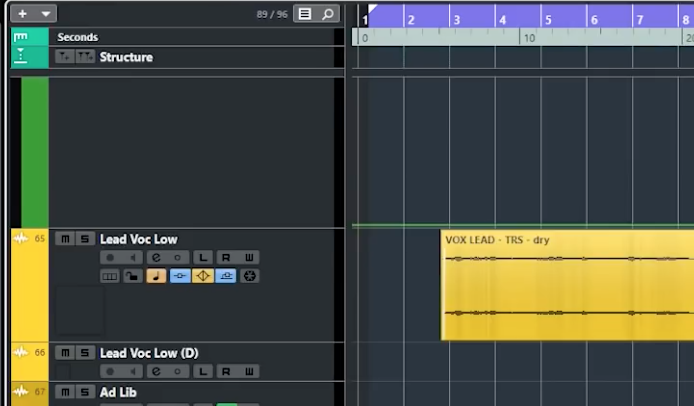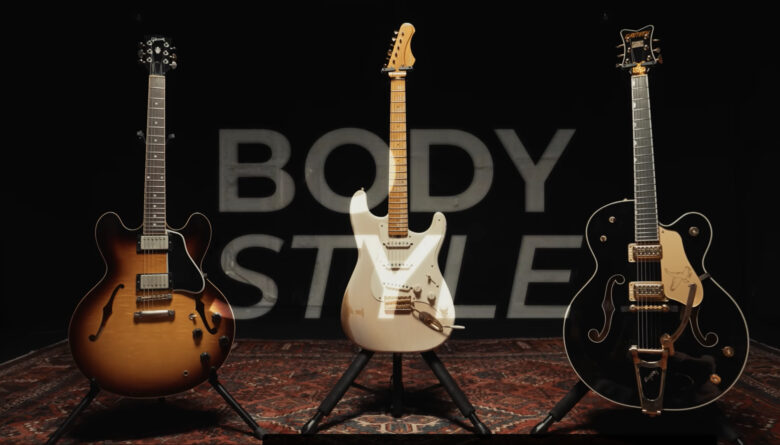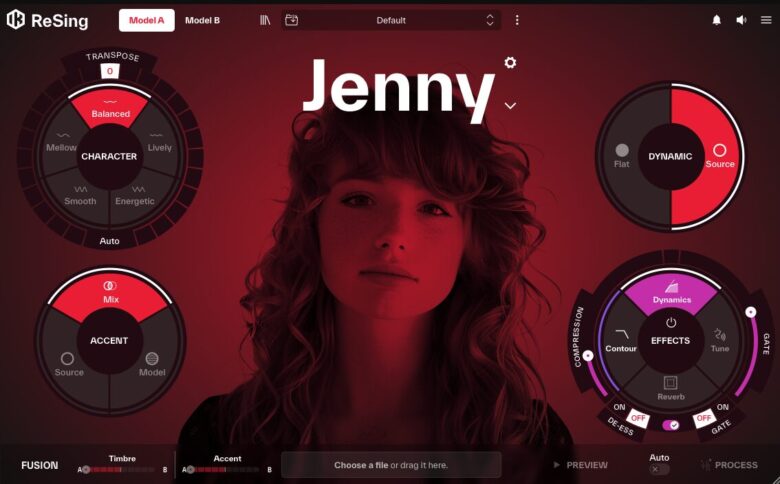今回は英語版wikipediaの「ビッグバンド」をまとめました。
この記事ではPart3として、ビッグバンドの歴史(現代のビッグバンド)について解説していきます。
現代のビッグバンド

ビッグバンドは「スイング時代のもの」と言われがちですが、ジャズミュージシャンたちはその後も活動しています。
しかし、スイングとは違ったスタイルで演奏することが多いです。
Charlie Barnetの活躍
バンドリーダーのCharlie Barnetの1942年の楽曲「Cherokee」や、1943年の「The Moose」は、「バップ時代」の始まりと言われています。
Woody Hermanの活躍
Woody Hermanの最初のバンド(ニックネームはFirst Herd)は、プログレッシブジャズを用いたスタイルが有名です。
2つ目のバンド「Second Herd」は、3本のテナーサックスと1本のバリトンで構成されるサックスセクションを推し出すスタイルが特徴的です。
Stan Kentonの活躍
1950年代になると、Stan Kentonは自身のバンドの音楽を「プログレッシブジャズ」「モダン」「新しい音楽」とし、彼の作曲活動の架け橋としてバンドを結成します。
Kentonは衝突するような要素を組み合わせたり、音楽的な考えた対立するアレンジャーを自ら雇うことで、ビッグバンドの境界をさらに押し広げます。
このような多方面的な考え方は、第二次世界大戦後のジャズを多く特徴付ける要素の一つです。
Sun Ra and his Arketstra
1960年代から1970年代の間は、「Sun Ra and his Arketstra」がビッグバンドをさらに盛り上げていきます。
彼らの多方面的な音楽は、10~30名のミュージシャンたちによって演奏され、衣装、ダンサー、特殊効果を備えた演劇として上演されていました。
1950年代から1970年代の間に活躍したジャズバンド
ジャズは1950年代から1970年代の間どんどん拡大していきましたが、その間もBasieやEllingtonのバンドは活躍していました。
他にも、Buddy Rich、Gene Krupa、Lionel Hampton、Earl Hines、Les Brown、Clark Terry、Doc Severisenなどが率いるバンドも活躍していました。
プログレッシブバンドでは、Dizzy Gillespie、Gil Evans、Carla Bley、Toshiko Akiyoshi and Lew Tabackin、Don Ellis、Anthony Braxtonなどのバンドが活躍していました。
新しいジャズの形が続々と誕生する
また、他のバンドリーダーの中には、ブラジル音楽やアフロキューバンをビッグバンド編成の楽曲に取り入れる人物もいました。
アレンジャーのGil Evans、サックス奏者のJohn Coltrane、ベーシストのJaco Pastoriusなどは、クールジャズ(cool jazz)やフリージャズ(free jazz)、ジャズフュージョン(jazz fusion)などをビッグバンドの領域に広めていきます。
クールジャズ
クールジャズは第二次世界大戦後に生まれたジャズの一種で、よりリラックスしたテンポで、軽めのトーンで演奏されるのが特徴です。
フリージャズ
フリージャズは1950年代終わりから1960年代前半にかけて発展していったジャズで、いわゆる「普通のテンポ」「普通のトーン」「いつものコード進行」などの概念から離れ、新しい方向を生み出そうとしたミュージシャンたちによって生まれたスタイルです。
「他のジャンルや型にはまっていない」というのが大きな特徴です。
ジャズフュージョン
ジャズフュージョンは1960年代終わりに発展したジャズのスタイルで、ジャズのハーモニーや即興の要素と、ロック・ファンク・R&Bの要素を組み合わせた音楽です。
ジャズフュージョンにおけるアレンジの仕方は多岐に渡りますが、シンプルでも複雑なアレンジでも、基本的にはとても長い即興部分があり、「また違ったジャズの形」を感じさせるのが特徴的です。
現代のビッグバンドは、ジャズにおける全てのスタイルで演奏しています。
大編成の現代ヨーロッパジャズアンサンブルの中には、アバンギャルドジャズをビッグバンドの編成で演奏しているバンドもあります。
たとえば、1977年に設立されたVienna Art Orchestraや、1990年代に活動していたItalian Instabile Orchestraが挙げられます。
アバンギャルドジャズ
アバンギャルドジャズは、アバンギャルドアート音楽とジャズの作曲法を組み合わせた音楽で、1950年代に始まり、1960年代に発展しました。
スイングのリバイバル
1990年代終わりごろになると、アメリカでスイングのリバイバル(再度注目を集めるムーブメント)が起こります。
リンディーホップ(The Lindy Hop)が再度人気を集め、若者がビッグバンドスタイルに興味を持つようになりました。
また、ビッグバンドはアメリカのテレビ番組でも存在感を維持していきます。
特に早い時間帯の番組や視聴者が多い番組ではホーンセクション(主にサックス、トランペット、トロンボーン)を伴ったビッグバンドを用いており、遅い時間帯の番組では小さな編成のビッグバンドをBGMとしていました。
以上でビッグバンドの解説は終了です。
当サイトでは他にもビッグバンドに関連する音楽ジャンルについて解説していますので、ぜひこちらもご覧ください↓