今回は、Mastering.comが教える「もっと早く知りたかったミックスのコツ13選」をまとめました。
この記事・Part1では「1~3個目のミックスのコツ」をご紹介します。
解説者本人が「何で誰も教えてくれなかったの?」「これを知っていれば、ものすごく時間を節約できたのに…」と思うほど重要なTipsがたくさんありますので、みなさんもぜひマスターしてください!
ミックスのコツ1.「10/10ルール」を知る

https://youtu.be/gCbugYCROCo
1つ目のMIXのコツは「10/10ルールを知る」です。
「10/10ルール」とは、「ミックスで楽曲を10点満点にするためには、ミックスを始める前の時点で最低7~8点はないといけない」というものです。
実際に、グラミー賞受賞レベルのプロは10/10ルールに沿って制作しています。
グラミー賞を受賞したプロの楽曲を聞いてみると、ミックスを始める前の時点で既に「ミックスは必要ないのでは?」と思うぐらい良い音がしています。
10/10ルールを達成するためのミックスのコツ
10/10ルールを達成するためのコツは、「ミックス前の状態を”その時できるベストな状態”にする」です。

そうすれば、ミックスのときの負担やプレッシャーも減りますし、「ミックスは現時点でよいものを、さらによくするためのプロセス」だと考えることができるようになります。
逆にこれができなければ、ミックスに10時間~15時間、数日…それ以上かかってしまったり、最悪の場合は「完成しない」ということもあり得ます。
ミックスを始める直前にも「整理」が大切

レコーディングや打ち込みが終わり、いよいよミックスを始めるという時は、オーディオデータなどをDAWにインポートをするでしょう。
この時も、本格的にミックスのためのプラグインを使う前にフェーダーで音量バランスだけを調節したりなど、「プラグインを使わなくてもできること」をするとよいでしょう。
このように全体を整理してからミックスを本格的に始めると、ミックスの手間を省くだけでなく、トラック1つ1つが抱える問題をすぐに発見することができます。
ミックスのコツ2.「主観的要素」と「客観的要素」を考えながら制作しよう

音楽制作は、「主観的な要素(Subjective)」と「客観的な要素(Objective)」の2つに分けられます。
・右脳で考えるような、クリエイティブなこと
・感情的なこと
・直感的なこと
・左脳で考えるような、テクニカルなこと
・周波数帯域
・音量&ダイナミクス
・音楽理論
・プラグインの機能や仕組み
ミックスとマスタリングは主観的 or 客観的?

ミックスは「主観的要素と客観的要素をつなげる作業」と言えます。
対してマスタリングは、周波数帯域や音量レベルをチェックするなど、ほとんどが「客観的でテクニカルな作業」です。
音楽制作のほとんどはクリエイティブな作業が多く、ミックスはそれらを一旦整理するようなプロセスでありながら、アーティストが創作したものから意図や感情を汲み取り、クリエイティブ思考を活かした作業も行います。
そのため、よりよいミックスをするには主観と客観の両方のスキルが必要なのです。
ミックスは「クリエイティブ」と「テクニカル」をつなぐプロセス

以上を踏まえると、やはりミックスにおいて「主観」と「客観」を分けて考えることはとても大切だと言えます。
そのため、テクニカルなことばかり学ぼうとするのは止め、クリエイティブなこと=主観的なことも日々学んでいくようにしましょう。
例えば、「コンプレッサーはどのように動くのか?」「このパラメーターにはどんな役割があるのか?」などを学んでいくとよいでしょう。
当サイトでは、このような「なんとなくプラグイン・音源を使っている状態」を卒業するための記事を数多く用意していますので、ぜひご活用ください↓
どちらも学べば「ギターソロができる状態」
この主観と客観は、ギターソロに例えることができます。

「客観的要素をマスターしている」ということは、「指使いやスケールなどを間違うことなく、すぐに演奏することができる」という状態です。
主観的要素だけではアイデアがあってもすぐに演奏することはできませんし、客観的要素だけでは技術があっても人を魅了するフレーズをパフォーマンスすることができません。
両方あって、はじめてギターソロをすることができるのです。
ミックスのコツ3.「IS & OUGHT」の考え方を活かす
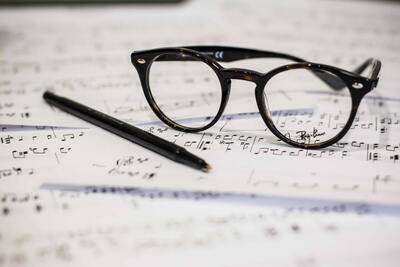
先ほどは「主観と客観」についてお話しましたが、次はこの「主観と客観を活かしていくか?」に関するコツ「IS & OUGHTの考え方を活かす」です。
この考え方は、スコットランドの哲学者David Humeの言葉からアイデアを得ました。
「Is」から「Ought」を導き出すことはできない
少し難しそうな文章ですが、噛み砕いて説明していきましょう。
「”Is”から”Ought”を導き出すことはできない」の意味とは?

「Is」はみなさんご存知のBe動詞で「〜である」「〜だ」という意味があります。
一方、「Ought」は「〜すべき」「〜するのが当然である」という意味があります。
例えば「A tree is green(木は緑色です)」と言われたとき、「Therefore you ought to cut trees down(したがって、木は切り落とすべきだ)」と言う人はいないでしょう。
「木は緑色だから切り落とさなければいけない」ということはないですよね。
言い換えると、「Is」で表していること=物事の状態や事実に対して、必ずしも「〜するべきだ」を意味する「Ought」を使うことはできないのです。
音楽制作に「Is」と「Ought」を活かすとどうなる?
これを音楽制作に活かすとしたら、どう考えられるでしょうか?
例えば2kHz付近の音を多く含んでいるスネアがあったとき、「この音は、2kHz付近の音を多く含んでいるスネアの音である」ということは、紛れもない「事実」です。
EQやアナライザーを見て2kHz付近を多く含んでいることが分かったら、それは純粋に「事実」であり、「客観的な要素」です。
しかし、この音に対して何をしていくかは、完全に主観的なプロセスになります。
「したがって、2kHz付近の音はカットするべきだ」
とは、誰も言えませんよね。
2kHz付近の音をカットするかどうか、どれぐらいカットするかどうかなどはすべて「主観的な要素」であり、みなさんの手に委ねられていることだからです。
ミックスで考えるべきなのは「ゴール」

みなさんがミックスで考えるべきなのは、「ゴールに対して何ができるか?」です。
例えば先ほどのスネアの例で言うと、「ボーカルの2kHz付近がマスキングされないよう、2kHz付近にもう少し多く空きを作りたい」というゴールがあるのであれば、スネアの2kHz付近はカットするべきでしょう。
しかし、スネアの2kHz付近をカットする以外にもたくさん方法はあるので、必ずしもスネアに対して処理しなければいけないということでもありません。
ミックスのゴールを決めるコツ「リファレンス曲を使う」

ミックスにおいてゴールを設定することは大切ですが、この時に効果的なのが「リファレンス曲を用意する」です。
自分が作っている曲と似ている曲のうち、「いいな」「こういうサウンドにしたい」と思える曲を見つけて、その曲と比較しながらミックスを進めていきましょう。
「いい音かどうか」は完全に主観的な要素ですので、客観的に「いいかどうか」を判断することは難しいですが、少なくとも自分の曲を「いい曲」に近づけやすくなります。
ミックスのゴールを決めるもう一つのコツ「自分の感情をガイドにする」

ミックスのゴールを決めるにあたり、リファレンス曲を使う方法よりももっと主観的な方法があります。
「自分の感情をミックスのガイドにする」です。
・この曲は何を表現したくて作った曲か?
・この曲を聞いたとき、どんな感情になるか?
・どんな感情になって欲しくて作っているか?
以上のようなことを、ミックスをするときに考えながらやってみましょう。
自分の感情をガイドにする実際の例

例えば実際にやってみると、このようになります↓
「ちょっと生意気な感じ」
「セクシーな感じ」
「曲が進んでくると、ここではエネルギーが盛り上がってくる」
「ちょっとレイドバックする感じ」
「サビはもっとパンチがある感じがいいな」
「最初はもっと元気があったほうがいい」
「現時点ではBusにコンプレッションがかかっているから、これをもう少し強くすればかんたんにパンチを加えられるな」
「試しにWaves社のコンプ「api-2500」を使ってみよう」

https://youtu.be/gCbugYCROCo
↓api-2500を使った例
「コンプのアタックが遅いと、スネアとキックにパンチが加えられるな」
「スレッショルドをだんだん下げてみると、いい感じになるな」
このように、聞いたときに出てきた自分の感情に従ってミックスを進めると、それだけでも自分の理想・ゴールに近づけることができます。
自分の感情をガイドにすると「自分らしさ」「オリジナリティ」が出せる

自分の感情に従ってミックスを進める場合は、リファレンス曲を使うときよりも「自分の好き嫌い」が顕著になります。
自分の感情=自分の好み・テイストになりますので、自分の「好き」に従って曲作りをしたいときにはおすすめです。
そのためにも、時間をかけて何曲もミックスを練習したり、いろいろな曲を聞いたりして「自分の中にある基準=Internal Refernece」を開発していくことが大切です。
Part2・4~6個目のミックスのコツはコチラ↓












