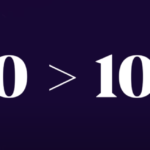かんたんにできる「MIXのコツ」ってないの?
今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。
今回は初心者向けの内容ですので、とりわけ難しいものはありません。
どれも今日からすぐ実践でき、効果もバツグンですので、ぜひお試しください!
初心者のためのMIX(ミキシング)のコツ5つ

2.パラレルコンプレッション
3.パン(Pan)振りで厚みを出す
4.休憩を取る
5.エフェクトの順番を工夫する
それでは1つずつ見ていきましょう。
MIX(ミキシング)のコツ1.Busを使う

1つ目のコツは「Busを使う」です。
初心者の方には、「トラックのフェーダーは、各トラックそれぞれを上げ下げするものだ」と思っている人もいるかもしれません。
トラックを1つのグループとしてまとめることもできます。
Bus(バス)って何?
Bus(バス)というのは、かんたんに言うと「複数トラックを1つのトラックにまとめるための”出口”」です。
たとえば、ボーカルが5人いる曲の場合を想像してみましょう。
ボーカル1人につき1トラック使うと、合計で5トラックになります。
このとき「5人全員の音量を-3dB下げたい」と思ったとしましょう。
5トラックそれぞれのフェーダーをぴったり-3dBずつ下げるのは…ちょっと面倒ですよね。
一斉に同じ処理を加えたいときにBusが使える
ここで、「Vocal Bus」というBusを作りましょう。
(作り方は各DAWで異なりますので、「DAW名 Bus」「DAW名 グループトラック」などで調べてみてください)
そしてこの5トラックの出口、つまりOutputを「Vocal Bus」にしてみます。
すると、Vocal Busのボリュームフェーダーを上げ下げすると、5トラックすべてのボリュームが同様に上げ下げされます。
全トラックに同じエフェクトをかけたいときにもBusが使える
Busを使って変えられるのは、ボリュームなどフェーダーを使った操作だけではありません。
エフェクトやパン、オートメーションなども使えるのです!
たとえば先ほどの例で、ボーカル5トラックに、全く同じリバーブとディレイをかけたいと思ったとしましょう。
そのとき、いちいちそれぞれのトラックにリバーブとディレイを設定するのは...ちょっと面倒ですよね。
ここで、Vocal Busにリバーブとディレイを使ってみましょう。
ボーカル5トラックはすべてVocal Busにまとめられていますから、このBusにリバーブとディレイをかけてしまえば、すべてのボーカルトラックに同じエフェクトがかかることになります。
基本的にはすべてBusにまとめよう
基本的には、トラックは一旦Busにまとめ、もともとのトラックは直接Master(Stereo Out)に行かないようにしましょう。
(Bus = Vocal BusやDrum Busなど、パート別のBus)
つまり、Master(Stereo Out)につながるのはMIX Busだけにしておこう、ということです。
MIX(ミキシング)のコツ2.パラレルコンプレッション

2つ目のコツは「パラレルコンプレッションを使う」です。
パラレルコンプレッションとは、「コンプレッサー(以下コンプ)がかかった音と、かかっていない音を混ぜる」というテクニックです。
パラレルコンプレッションのやり方
たとえば、ドラムのスネアにパラレルコンプをしたいときの場合。
(これはMIX Busとはちょっと違います。Sendで送るので、元の音はMasterに、Sendに送った音はSendトラックから出ます。)
2.スネアを送ったSendトラックに、コンプレッサーを追加する
こうすると、スネアの音はこの2つの音が混ぜられることになります。
→もともとの演奏にあったダイナミクス(抑揚)をキープする役割
→コンプをかけたことで、音に圧が出る=厚みが出る。
つまり、それぞれの音のいいとこ取りができます。
ちなみに2つの音量バランスは、必ずしも50対50にする必要はありません。
お好みの音になるよう、Sendの量を調整してみてください。
↓パラレルコンプの音の違い(1:38~)
パラレルリバーブとは?
リバーブを使うときは、いらない低域を削るためにハイパスフィルターを使うことが多いと思います。
(リバーブの低域は、音をにごらせる原因になることがあります)
実はこれも、パラレルコンプと同じ原理で調整することが可能です。
いわゆる「パラレルリバーブ」です。
パラレルリバーブのやり方
やり方は、パラレルコンプと全く同じです。
1.リバーブをかけたいトラックを、パラレルリバーブ用のSendトラックに送る
2.パラレルリバーブ用のSendトラックにリバーブを追加する
(このとき、ハイパスフィルターはかけない=低域は残しておく)
3.リバーブをかけたいトラックのSendの量を調節する
MIX(ミキシング)のコツ3.パン(Pan)振りで厚みを出す

3つ目のコツは、「パン(Pan)を振って厚みを出す」です。
厚みのあるサウンドにするために使えるのがこのテクニック。
やり方は非常にかんたんです。
2.2つのトラックのうち、片方は一番左に、もう片方を一番右にPanを振る
3.音が真ん中に聞こえてしまう場合は、片方にChorusやFlangerなどのモジュレーション系エフェクトを使うか、ほんの少しタイミングをずらす
パートによって良し悪しは変わる
このテクニックは、パートによって合うか合わないかが大きく変わります。
たとえばボーカルやドラムなら、このテクニックを使わず、そのまま真ん中で鳴らした方がよいことが多いです。
一方、バッキングボーカル(ハモリ等)や他の楽器なら、このテクニックはピッタリ合うでしょう。
MIX(ミキシング)のコツ4.休憩を取る

4つ目のコツは、「休憩を取る」です。
何かを長時間聞いていると、特に大きな音で聞いていた場合、音量に対する判断が鈍ってきます。
これはいわゆる「耳の疲労」で、MIXにおいて悪い判断を下す原因になります。
耳の疲労を避けるには?
通常の音量でMIXをしている場合は、2時間に1回、15分の休憩を取ることをおすすめします。
また、作業中はよりクリアに音を聞くために、どんどん音量を上げている人もいるかもしれません。
ちなみに耳の疲労を避ける具体的なテクニックは、こちらでも紹介しています。
MIX(ミキシング)のコツ5.エフェクトの順番を工夫する

5つ目のコツは「エフェクトの順番を工夫する」です。
これはサウンドに関わる非常に大切なことなのですが、意外と見過ごされやすいのです...
たとえばディレイの前にリバーブが来ると、スペース感を感じさせるエコーの効果がより加わりやすいです(4:16~)。
逆にリバーブの前にディレイをかけると、エコーの回数がより増えます(4:24〜)。
MIX(ミキシング)をさらにレベルアップしたい方へ
以上でミックスのコツ5つ」の解説は終了です。
よりアドバンスなMIXのコツはこちらの記事でもまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓