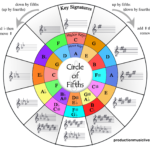今回は、Pyramindのインストラクター・Ryan Reyが解説する「五度圏(サークルオブフィフス)を活用する5つの方法」をまとめました。
この記事では、その活用法の2つ目「ダイアトニックコードを確認する」をご紹介します。
「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ
「五度圏」と聞くと、なんだか難しそうな音楽理論の話に聞こえるかもしれません。
しかし、そもそも五度圏を知らないという方にも理解できるように、できるだけ噛み砕いて説明していますのでご安心ください。
ダイアトニックトライアドを確認する
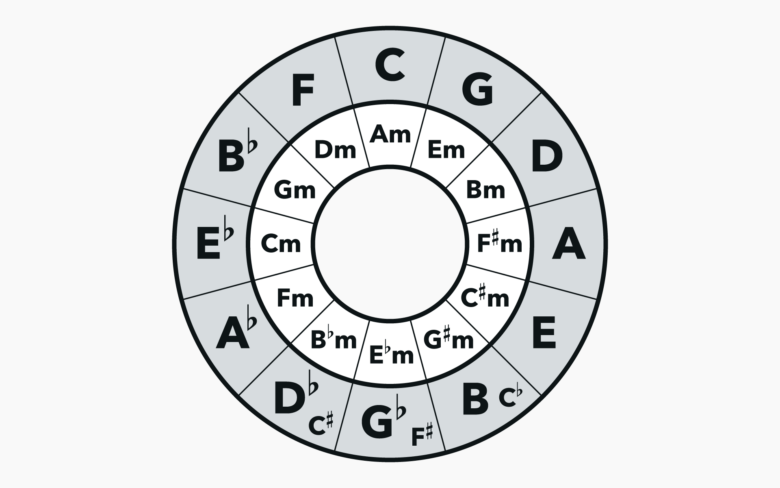
この五度圏は、ダイアトニックトライアドを確認するのに使えます。
言い換えると、そのスケールでよく使われるコードを把握するのにとても役立ちます。
トライアドとは?

ルート音・3度・5度の3つの音で構成された和音を指します。
たとえばC・E・G(ドミソ)や「E・G#・B(ミ・ソ#・シ)」などです。
ダイアトニックトライアドとは?

ダイアトニックトライアドとは、スケール上にある音のうち、ルート音・3度・5度の3つの音で構成された和音のことをいいます。
Cメジャーキーでの例
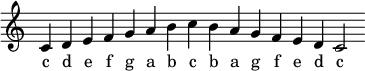
Cメジャーキーは、#もbもついていません。
つまりこのキーでは、ピアノの鍵盤でいうと白鍵のみを使い、黒鍵は使いません。
ということは、Cメジャーキーのトライアドは、どの音をルートにしたときもすべて白鍵の音で成り立つ、ということになります。
実際に確認してみましょう。
Cメジャーキーのトライアドはこのようになります。
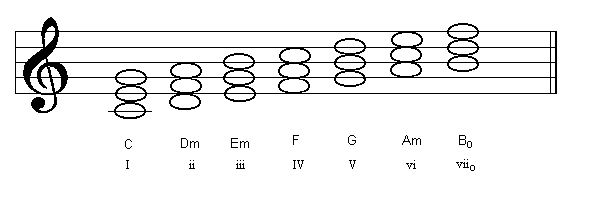
引用:http://www.cyberflotsam.com/images/Music_Triad1-1.gif
ピアノで弾く場合は、「ド・ミ・ソ」の手の形をそのまま右にずらしていくだけです。
メジャーコードとマイナーコードもわかる

実は五度圏の表を見るだけで、そのダイアトニックコードがメジャーコードになるのか、マイナーコードになるのかもわかります。
メジャーキー(外側の円)の場合、その音と左右にある音がルートになるときにメジャーコードになります。
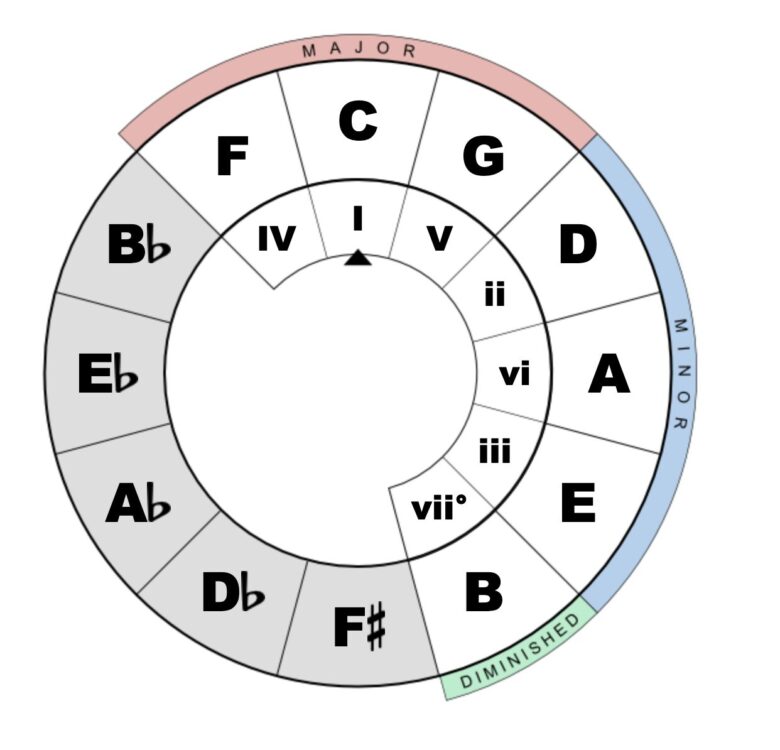
こちらの図が非常にわかりやすいです。
対象のスケールの1つ左から数え始めて、メジャー3つ→マイナー3つ→ディミニッシュという順番で並んでいます。
これを理解すれば、もうコードの種類で迷うことはないでしょう。
Cメジャーキーでの例
Cはもちろんメジャーコードになりますが、Cの左右にあるFとGのときもメジャーコードになります。
C(1th):ド・ミ・ソ
F(4th):ファ・ラ・ド
G(5th):ソ・シ・レ
それ以外のときは、マイナーコードかディミニッシュコードになります。
Gメジャーキーでの例
では、Gメジャーキーの場合を見てみましょう。
Gメジャーキーでは、#が1つ、Fにつきます。
コードにおいては、Gはもちろん、Gの左右にあるCとDがルートのときにメジャーコードになります。
G(1th):ソ・シ・レ
C(4th):ド・ミ・ソ
D(5th):レ・ファ#・ラ
ついでに平行調のコードも確認する
前回の「スケール編」で、平行調の解説をしました。
ざっくり言うと、平行調とは同じb・#数のメジャーキーとマイナーキーのことです。
たとえば、Cメジャーキーの平行調はAマイナーコードです。
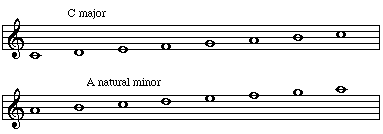
どちらも、bと#が0個のスケールです。
つまり、さきほどのこの五度圏表を見れば、平行調のダイアトニックコードも確認できます。
たとえばCメジャーキーのときにマイナーコードになっているなら、Aマイナーキーのときもマイナーコードになることがわかります。
マイナーキーは円の内側に書かれていますが、この場合はその音と、左右となりの音がルート音のコードのときにマイナーになります。
並び方はメジャーキーと同じですが、ルート音(先ほどの画像における矢印)の位置が異なります。
ついでにスケール音も確認する
各スケールは全部で7音ありますが、どの音をどのスケールで確認するかもチェックできます。
さきほどの例だと、メジャー・マイナー・ディミニッシュ、いずれかに属している音はそのスケールに入っている音です。
五度圏におけるダイアトニックコードの確認方法まとめ
今回もボリュームたっぷりお届けしましたが、内容をまとめるとこのようになります。
メジャーキー(外側の円)の場合、その音と左右となりの音がルート音になるとき、メジャーコードになる
マイナーキー(内側の円)の場合、その音と左右となりの音がルート音になるとき、マイナーコードになる
(いずれの場合も、平行調も同じダイアトニックコードになる)
次回、活用法3つ目は「近親調」に関する内容です🔻
「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ