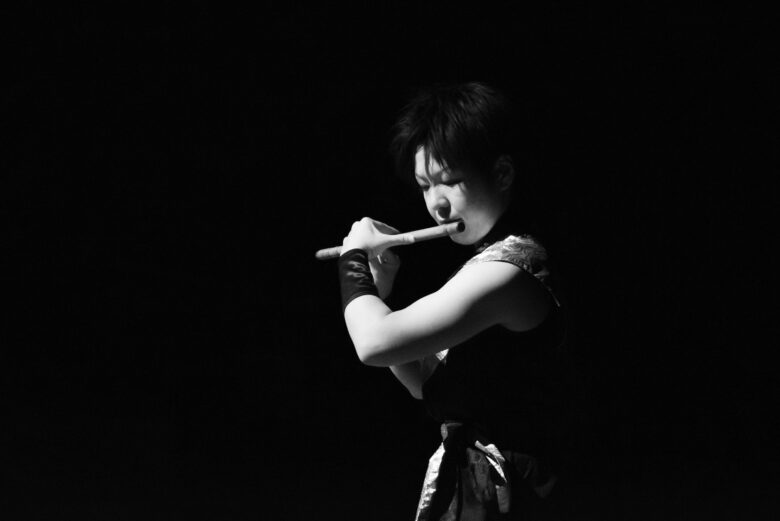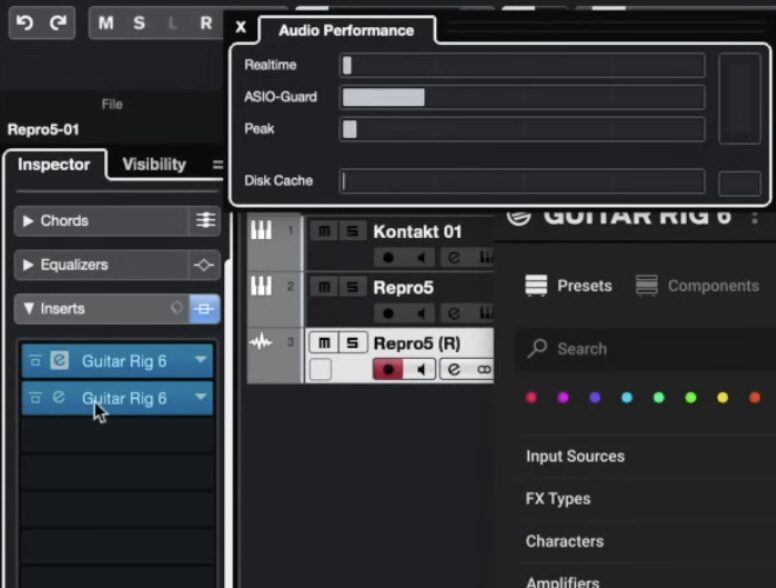今回は英語版wikipediaの「スカ(Ska)」をまとめました。
日本では「東京スカパラダイス」でおなじみのこのジャンルについて、詳しく解説していきます。
カリビアンミュージック解説シリーズ
スカ(Ska)って?
スカは、1950年代終わりにジャマイカで誕生した、ロックステディやレゲエの前身となる音楽スタイルです。
(ロックステディはPart5で、レゲエはPart6でご紹介しています)
Part2とPart3でご紹介したメントやカリプソの要素に、アメリカのジャズやR&Bの要素を加えたのがスカです。
オフビートにアクセントを置いたウォーキングベースが特徴的。
日本では、東京スカパラダイスオーケストラがスカバンドとしてとても有名です。
「スカ(Ska)」という名前の由来
スカ(Ska)という名前の由来には諸説あります。
1.ギターをかき鳴らした時の音を表す言葉「Skat!Skat!Skat!」から来ている説
2.Coxsone Doddが1959年にプロデュースした楽曲のレコーディングにおいて、ダブルベース奏者のCluett JohnsonがギタリストのRanglinに「”ska, ska, ska”みたいに演奏して」と伝えたところから来ている説
(ただしJohnson本人はこの説を否定している)
3.Johnsonが友人に挨拶するときに使う言葉「skavoovie」から来ている説
4.ミュージシャンたちがリズムを「Staya Staya」と呼んでいる+Byron Leeが「Ska」という用語を導入し始めた説
5.ギターやピアノが「ska ska」というように演奏しているように聞こえるところから来ている説
スカの歴史
ここからは、スカの歴史について解説していきます。
スカはいつからできた?
1960年代は、Stranger Cole、Prince Buster、Clement “Coxsone” Dodd、Duke ReidがアメリカのR&Bをプレイする際に使った「サウンドシステム」を形成しました。
この1960年代にスカが発展し、スカ独自のレコードがリリースされていきます。
「サウンドシステム」は、ジャマイカのポピュラーカルチャーにおけるスカやロックステディ、レゲエをプレイするDJ、エンジニア、MCのグループのことです。
DJやエンジニア、MCが路上に大きなスピーカーを置いて、音楽を再生して多くの人々と楽しんでいました。
1960年代初期にはスカはジャマイカにおける主要な音楽ジャンルとなり、イギリスの「モッズ(Mods)」においてポピュラーもジャンルの一つとなります。
モッズ:イギリスのロンドンで発祥し、1950年代後半から1960年代中盤にかけて労働者階級の若者の間で流行した、音楽やファッション、ライフスタイルのこと、あるいはその支持者たちのこと。
この20年後には、同じくイギリスのロンドンで労働者階級の若者たちによって誕生した「スキンヘッド(skinhead)」の文化においても人気となります。
スカの歴史をざっくり分けると…
スカの歴史は大きく3つに分けられます。
1960年代:スカの誕生
1970年代後半:イギリスでの”2トーン”のリバイバル、「ジャマイカスカのリズム・メロディー」と「パンクロックの強いキレと速いテンポ」の融合、スカパンクの誕生
1980年代後半~1990年代:世界中を巻き込む「第三次スカブーム」
スカの誕生
ここからは、スカがどのように誕生したのかを解説していきます。
アメリカ音楽が身近にあった時代
第二次世界大戦後、ジャマイカの人々はより多くのアメリカ南部(ニューオリンズ)のR&Bを聞くため、多くのラジオを購入しました。
ここにおけるアメリカ南部のR&Bのアーティストには、 Fats Domino、Barbie Gaye、Rosco Gordon、Louis Jordanなどが挙げられ、彼らの初期の楽曲は、スカやレゲエに「ビートにちょっと遅れる(behind the beat)」の精神を与えることとなります。
(これらのアーティストやR&Bについてはこちらの記事で詳しく解説しています)
戦時中・戦後にアメリカ軍が駐留したことにより、ジャマイカの人々はアメリカ音楽の軍事放送を聞くことができたため、常にアメリカの楽曲を聴くことができました。
この音楽の需要を満たすために、前述のPrince Buster、Coxsone Dodd、そしてDuke Reidらが「サウンドシステム」を形成しました。
自分たちのスタイルで
1950年代後半になると、ジャンプブルースやより昔のR&Bなどで「今まで聞いたことがない音楽」とされてきた楽曲が枯渇し始めたため、ジャマイカのプロデューサーたちは地元のアーティストたちと共に、彼ら独自のスタイルでそれらの音楽を作り始めるようになります。
この頃は「ソフトワックス(soft wax)」で再生されるために作られますが、1959年後半になると需要が増えたため、Coxsone DoddやDuke Reidなどのプロデューサーたちは、45rpm 7インチディスクでのレコードの生産を始めます。
ソフトワックス:のちに「ダブ・プレート」という名前で知られる、メタルディスクにラッカー仕上げをしたレコード

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/Dubplate
この頃には、ジャマイカの音楽スタイルはアメリカの「シャッフルブルース」をコピーしたスタイルになっていましたが、この後2~3年以内には、オフビートに入るギターチョップを伴う、現在のスカにより近い形となります。
これは、以下のような1950年代後半にアメリカのR&Bで見られる、よりアップテンポなR&Bでも見られます。
ちなみにこの2つの楽曲「Be My Guest(Fats Domingo)」と「My Boy Lollypop(Barbie Gaye)」は、両方とも1950年代終わりごろのジャマイカのサウンドシステムでとても人気があった楽曲です。
Dominoの楽曲におけるリズムではオフビートにアクセントが置かれており、ジャマイカのスカがこのスタイルからとても影響を受けていることがわかります。
「クラシック・スカ」の特徴
このような「クラシックスカ(昔のスカ)」では1小節につき8分音符の3連符(1拍に3つ音を鳴らす3連)で成り立っていますが、ギターチョップとオフビートが特徴的です。
これらは「アップストローク」もしくは「スカンク(Skank)」と呼ばれ、同時にホーンセクションがリードを吹き、続いてオフビートのスカンク、ピアノによるベースラインを強調した演奏、そしてまたスカンクのセクション..と続きます。


画像:スカンクのギターのリズム(wikipediaより)
ドラムは4/4をキープし、バスドラムは各拍の3連符のうち3つ目にアクセントを置き、スネアはリムショットで、バスドラムと同じ位置にアクセントを置きます。
アップストロークは他のカリビアンミュージックでも見られ、メントやカリプソでも使われています。
ジャマイカのギタリスト・作曲家であるErnest Ranglinは、スカとR&Bのビートの違いについて「スカは「チン・カ・チン・カ」というリズムで、R&Bは「カ・チン・カ・チン」と表現しています。
ドラムは伝統的なジャマイカのドラミングやマーチのドラミングから来ています。
スカのビートを作るため、Prince BusterはR&Bのシャッフルビートを真逆にし、ギターのヘルプ要素でもあったオフビートの音を伸ばすようにしていきます。
Princeは、スカの起源としてアメリカのR&Bを非常にわかりやすく使っており、これはたとえば「Laterfor the Fator」などで見られます。
スカ最初の作品
最初のスカの作品は、ジャマイカのキングストンにあるFederal RechordsやStudio One、WIRL Recordsなどの場所でレコーディングされました。
これには、これまでの解説にも出てきたDoddやReid、Prince Buster、Edward Seagaなどが参加しています。
スカのサウンドは、1962年にイギリスから独立したことに関係する祝福の気持ちと一致しており、Derrick Morganの「Forward March」やThe Skatalitesの「Freedom Sound」などの楽曲でお祝いする記念イベントもありました。
カバー作品
ジャマイカが文学・美術的著作物の保護に関する条約「ベルン条約」を締結するまでは、国では国際的な音楽著作権保護を尊重していませんでした。
このため、この時代は多くのカバー曲や「再解釈」などが行われます。
有名なカバーには、Millie SmallのR&B・シャッフルチューンである「My Boy Lollypop」があり、これは当時14歳のBarbie Gayeが1956年にニューヨークでリリースした作品です。
このSmallのリズム的に似たバージョンは1964年にリリースされ、これはジャマイカ初、商業的に世界でヒットした最初の例となりました。
700万枚以上を売り上げ、今でもレゲエ・スカソングで最も売れた作品となっています。
他にも、以下のように多くのジャマイカ人アーティストたちがアメリカやイギリスのポピュラーソングや映画音楽などをスカで使う楽器を用いてカバーし、次々とヒットを出していきます。
もちろん彼ら自身のオリジナル版も制作し、Mongo Santamaríaなどのアーティストからラテンの影響を受けて楽曲が作られていくこともありました。
1965年から1966年ごろは、アメリカのソウルミュージックもよりゆっくり、スムーズな音楽へと変化していき、スカもその影響を受け、のちに「ロックステディ」という新しいジャンルへと発展していきます。
しかしロックステディのの全盛期は1967年のみで、1968年には、スカは次は「レゲエ」へ進化していきます。
2トーン(2 tone)時代
2トーンは、1970年代終わりにイギリスのコベントリー地域(南中部)で始まった、ジャマイカのスカのリズムと、パンクロックの非常にアグレッシブなギターのコード・歌詞を融合させた音楽ジャンルのことです。
1960年代のスカと比べると、2トーンはより速いテンポで、楽器の音で埋め尽くされ、かなりエッジが効いた音楽スタイルです。
このジャンルの名前は「2 Tone Records」というレコードレーベルの名前が由来です。
昔のスカの楽曲は、イギリスで作り直されたのちに再びヒット曲となることが多いです。
2トーンで取り上げられる話題
この2トーンのムーブメントは、イギリスで人種的な緊張感のあったこの時代に人種統一にも貢献しました。
当時はこういった人種問題や戦い、友好問題について気づきを得させる楽曲がたくさんあったのです。
イギリスの都市での暴動は、The Specialsの楽曲「Ghost Town」で取り上げられ、遅いテンポのレゲエビートでありながらヒットとなります。
2トーンで有名なバンド
多くの2トーンバンドは人種混合のグループで、たとえばThe BeatやThe Specials、The Selecterなどが挙げられます。
また、Madnessも有名な2トーンのグループです。
この時代の音楽は、歌詞に書かれていることと同じ経験をしたことなる白人の労働者階級の若者や西インドの移民たちによって大きく支持されていきます。
第三次スカブーム
第三次スカブームは1980年終わり頃のパンクのシーンで起こり、1990年代には商業的に成功することとなります。
この時代に作られたスカの中には、いわゆる昔の1960年代のスカのサウンドを使ったものもありますが、このブームの間では、よりギターリフやビッグなホーンセクションを使っているのが特徴です。
第三次スカブームで有名なバンド
おまけ:スカ・レゲエ・ロックステディの違いは?
ちなみにこちらの動画では、レゲエで有名なボブ・マーリーが「スカ」「レゲエ」「ロックステディ」の違いをとてもわかりやすく表現しています。
スカ:ンチャ・ンチャ・ンチャ・ンチャ(速いテンポで)
ロックステディ:チャー・ン・チャー・ン
レゲエ:チャッタ・タッタ・チャッタ・タッタ
次は同じくカリビアンミュージックの一つ「ロックステディ」について解説します↓