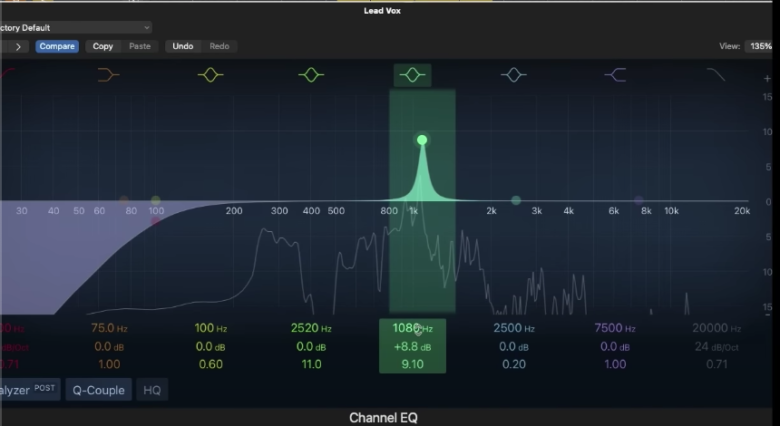ギターの「ピックアップ」って何?
どんなはたらきをするの?
このような疑問にお答えする内容です。
YAMAHAが解説する「ギターの"ピックアップ"とは?」をまとめました。
ギターのうちのたった1つの小さなパーツですが、非常に重要な役割を果たしています。
構造を知れば、自分で好みのギターにカスタマイズすることも可能ですので、ぜひ参考にしてください。
ピックアップの中身は「磁石とコイル」
ピックアップは、ギターにおける心臓部分と言えるでしょう。
ピックアップは、弦の振動を電気に変えるもので、ギターのボディーの弦の下に付けられています。
また、ピックアップは「コイル」を使っています。
そう、みなさんが学生の時に理科の授業で習った「コイル」です。

画像:元記事より
エレキギターのピックアップは、6つの磁石の棒が差し込まれた黒いボビン(糸巻き)でできています。
また、エナメルワイヤーなどの素材は磁石に巻き付けられています。
この6つの磁石は、6本の弦からしっかり音を拾うために使われています。
ピックアップの中には、マグネットの代わりに金属の棒(メタルロッド)が使われているものもあります。
この場合は、長くて細いマグネットがボビンの下に備わっています。
なぜコイルを使うのか?
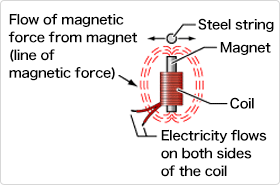
画像:元記事より
コイルは電話や手持ちマイクなどにも使われているものですが、コイルと磁石は、電力なしで音を電気に変えることができます。
磁性体が磁石とコイルの間を移動すると電流が流れるため、これが可能なのです。
エレキギターにおいては、スチール弦はこの「磁性体」のようなはたらきをします。
弦が振動する頻度によって、電流に変化が起こるのです。
弦の音の波の頻度と電流の波は一緒にはたらきますが、ピックアップはこの性質を利用して、音を電気に変えています。
コイルの巻き方のポイントは「巻かれている回数」と「密度」
コイルのはたらき方は非常にシンプルで、鳴る音はコイルが何回巻かれているか、そしてその巻き方によって変わります。
コイルをたくさん巻けば巻くほど、音の音量は大きくなります。
しかし、巻きすぎると音がはっきり聞こえなくなる(音を殺してしまう)のです。
何百回、何千回とコイルを巻いた場合なら、その後コイルをさらに十数回巻いても音は変わってくるでしょう。

一方、「コイルの巻き方」に関して言うと、「最初に巻いた後に、巻線の間にどれぐらい隙間が空いているか?」が重要になります。
その「隙間のサイズ」は非常に小さく、1/100mmの世界です。
この隙間が大きいと、高音が改善されます。
巻く高さや巻いた時の表面部分の状態もまた、音に影響が出ます。
ノイズキャンセリングができるピックアップ
エレキギターのピックアップは、1個~2個のコイルが使われます。
コイルが1つの場合は「シングルコイルピックアップ」と呼ばれ、2個の場合は「ハムバッキングピックアップ」と呼ばれます。

画像:シングルコイルピックアップとバッキングピックアップ(https://equipboard.com/posts/best-humbuckers)
コイルは外部からのノイズに影響されやすいのですが、ハムバッキングピックアップのようにコイルが2つある場合は、それぞれのノイズを打ち消し合い、ノイズを軽減することができるのです(ノイズキャンセリング)。
逆に、シングルピックアップはこのようなノイズキャンセリングの機能はありません。
しかし、パリっとクリーンな高音が出せます。
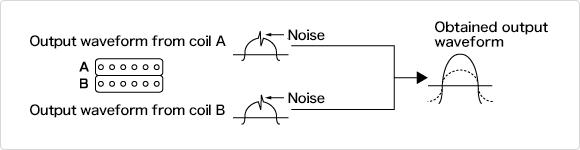
画像:記事より
ノイズは、コイルがどのように・何回巻かれているかによって変わってきます。
コイルが2つある場合、コイルAとコイルBは逆方向に巻かれ、これによってノイズキャンセリングが可能になります。
このとき、磁極の向きの方向が反対なので、位相がまっすぐになる=ノイズキャンセリングされるのです。
自分でピックアップを選んでみよう
今回ご紹介した知識を使えば、楽器店でバラ売りにされているピックアップを使って、自分好みのギターを作ることができます。
たとえばサウンドハウスではこのようなピックアップがたくさん売られていますので、ぜひチェックしてみてください。


以上で解説は終了です。
当サイトでは他にもギターやベースに関する記事をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓