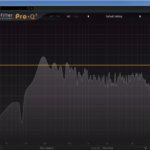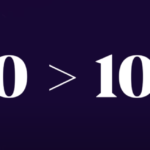今回は、In The Mixが解説する「この10年で学んだミックスのアドバイス」をまとめました。
解説者・マイケルがはじめてMIDIキーボードを触ったその日からプロとして活躍する今日までの10年間、さまざまな経験を通して学んだミックスのコツ・アドバイスを7つご紹介していきます。
この10年で学んだMIXのコツ7選

今回ご紹介するこの10年で学んだMIXのコツ7選はこちらです。
MIXのコツ7選
- ミックスの問題はミックスのせいではないかもしれない
- 位相問題は楽曲を台無しにする
- 「5クリックルール」を活用しよう
- 音圧戦争は終わっている
- ソロで聞くだけでは不十分
- 機材ではなく耳の問題
- ネットにあるアドバイスの99%は無意味
それでは、1つずつ解説をしていきます。
MIXアドバイス1.ミックスの問題はミックスのせいではないかもしれない

1つ目のアドバイスは、「ミックスの問題はミックスのせいではないかもしれない」です。
DTMerによくあるお悩みの1つが「同じ周波数帯域の楽器同士がぶつかってしまい、マスキングしてしまう」という問題です。
このようなマスキング問題を解決するため、soothe2やPro-Q3などの便利なEQプラグインを使ってどうにか調節しようとする人もいるでしょう。
確かにこれらのプラグインは非常に便利ですが、もしかするとそのミックスの問題はミックスのやり方にあるのではなく、そもそものアレンジやソングライティング(作曲)に問題があるかもしれません。
実際に世の中にある素晴らしい楽曲を聞くと、作曲・編曲が巧みに作られており、1つ1つの楽器や音符が上手に絡み合っていいグルーヴを生み出していることが多いです。
もはや、この作曲や編曲の段階ですでにミックスがされていると感じられるほどです。
プリセットはフルレンジである場合が多い
とは言え、特にシンセサイザーのプリセットははじめからフルレンジで作られており、低音域から高音域までが豊富に含まれていることが多いです。
そのため、プリセットのよさを壊さないようにEQで不要な音域をカットするなどして調整することも大切です。
MIXアドバイス2.位相問題は楽曲を台無しにする
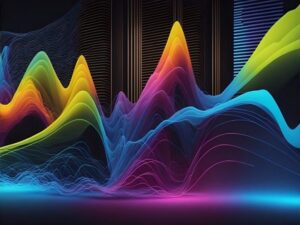
2つ目のアドバイスは、「位相問題は楽曲を台無しにする」です。
位相問題(位相の打ち消し)とは、複数の音を重ねたとき、音の波形の波が真逆に重なってしまい、それぞれの音が聞こえにくくなってしまうことです。
特に、低音域を含む音を扱うときは非常に注意が必要です。
「位相問題」と聞くと、自分でレコーディングしたオーディオデータを使うときに発生すると思いがちですが、実はSpliceなどのサンプルを使うときにも発生します。
そのため、自分でレコーディングするかどうかに限らず、オーディオデータを扱う場合は常に気をつけなくてはいけません。
実際に、どうしてもキックとベースを同時に鳴らすと迫力が出ず、新しくサンプルをレイヤーしたりEQやエキサイターを使っても解決しなかったものが、キックの位相を反転させるだけで解決した、ということもあります。
MIXアドバイス3.「5クリックルール」を活用しよう

3つ目のアドバイスは、「5クリックルールを活用する」です。
これは、DAW上で行う操作に5クリック以上必要になる場合は、「ショートカットを使う」「自動化する」「別の便利なソフトウェアに移行する」のいずれかを行うというルールです。
例えば、プリセットを選ぶのにいちいちメニューを開いてカテゴリを選んで調整して…などの手順を行っていると、プリセットを1つ選ぶのに時間がかかり、何度もクリックして手が疲れますし、イライラすることもあります。
このように「普段何気なくやっているけれど、実はストレスを感じている動作」というのは誰しもあるはずです。
そこでネットで調べると、便利なショートカットやツール、機能があることが多いです。
もし普段よく使う操作に5クリック以上必要になっている場合は、簡略化・自動化できないかどうか調べてみましょう。
自動化・ショートカット化できる機能の例
・追加・削除・移動系の操作(トラックや小節の追加など)
・ボーカルのピッチを補正する(自動ピッチ補正機能)
・プリセットやエフェクトチェインの保存
DTMの作業効率を上げる「Stream Deckを使った打ち込み方法」はこちらでまとめています↓
MIXアドバイス4.音圧戦争は終わっている

4つ目のアドバイスは、「音圧戦争は終わっている」です。
少し前までは「音圧(ラウドネス)は高ければ高いほどいい」という風潮がありましたが、もうその時代は終わっています。
今では「作品のクオリティを最大限に引き上げることができる音圧」であることがスタンダードです。
逆に言えば「作品のクオリティを崩さないギリギリの音圧にする」とも言えます。
これを聞くと「じゃあマスタリングエンジニアなんていらない。自分でマスタリングしていいのではないか?」と思うかもしれません。
しかし、プロのマスタリングエンジニアはみなさんの楽曲にとってベストなマスタリングについて、いくつかの選択肢を提供してくれることがあります。
自分では思いつかないようなマスタリングを、高品質で提供してくれますので、「マスタリングエンジニアはいらない」ということにはならないでしょう。
MIXアドバイス5.ソロで聞くだけでは不十分

5つ目のアドバイスは、「ソロで聞くだけでは不十分」です。
あるトラックだけを聞くために、ソロ(Solo)にして確認することは多いでしょう。
ソロで聞くことは、エフェクトなどの自分が行った処理の効果を確認することには非常に役立ちます。
そのため、「ソロで聞けばとてもいい音に聞こえる」ということもあります。
しかし、ソロで聞いて「いい」と思えても、楽曲全体で聞くとまとまりがなく、フィットしないように聞こえてしまうことがあります。
ミックスでは他のパートも一緒に聞きながら処理をしよう
このようなミスを防ぐには、エフェクトを加えるときはソロではなく、他のパートも一緒に聞きながら調整するのがおすすめです。
例えばスネアにリバーブをかけるときは、ドラム全体を鳴らしながらリバーブの量を調整してみましょう。
またボーカルを調整するときは、音域が近いギターやシンセサイザーを一緒に鳴らしながら調整してみましょう。
こうすると「ソロで聞く→全体で聞く」という作業を短縮できるため、音を聞く時間も減り、耳の疲労も減らすことができます。
MIXアドバイス6.機材ではなく耳の問題

6つ目のアドバイスは、「機材ではなく耳の問題」です。
DTMをしていると、「何かがうまくいかないのは使っている機材が高価なものではないからだ」「十分な機材が揃っていないからだ」と思ってしまいがちですが、必ずしもそうとは限りません。
確かに、質も値段も高い機材は楽曲のクオリティを上げてくれることがあります。
実際に、僕(マイケル)も音楽制作を始めた頃はひどい音質のスピーカーを使っており、そのせいで音を正確に聞き取ることができませんでした。
それが、いいスピーカーを購入してから劇的に音楽のクオリティを上げることができたのです。
しかし、中にはスキルさえあれば十分にできることもあります。
まさに「弘法筆を選ばず」のような場面もたくさんあり、機材ではなく耳のよさがキーポイントになることもあります。
まだ十分な音楽制作環境をお持ちでない方も、「安い機材しか使えないから自分はダメなんだ」と思わず、「この環境でもできることはないか?」「今の状態で工夫できることは何だろうか?」と考えてみましょう。
MIXアドバイス7.ネットにあるアドバイスの99%は無意味

7つ目のアドバイスは、「ネットにあるアドバイスの99%は無意味」です。
僕自身がこのようにしてネット上でミックスのアドバイスをしているので、一体何なんだと思うかもしれませんが…
すでにある程度の知識や技術をお持ちの方であれば、そのアドバイスが有意義なものかを判断することができます。
しかし、特に初心者の方は、まだ十分な知識やスキルをお持ちではないので、そもそもネット上に書かれているミックスのアドバイスが正しいかどうかを判断するのが難しいでしょう。
実際に僕自身も昔はネット上に落ちているミックスのアドバイスに従って曲を作っていて、役に立つものもありましたが、役に立たないものも試していたので、かなり時間を無駄にしました。
プロになった今思えば、本当に無意味なアドバイスだったと思うような内容です。
例えば「コンプレッサーはゲインリダクション量が3dBを超えないようにしよう」というアドバイスが至るところで言われていますが、プロの世界に入って、このアドバイスがナンセンスだということがわかりました。
結局は「その音楽にとって必要な分だけコンプレッサーをかければいい」という話なので、「何dB以上はダメ」のような具体例はあまり意味がありません。
特に、数字や公式を使ったアドバイスには要注意です。
オンラインの「ミックス学習コース」のようなものでもこのようなアドバイスをしていることがあるので、有料コンテンツでも注意が必要です。
この10年で学んだ7つのMIXのコツまとめ
以上が「この10年で学んだ7つのMIXのコツ」でした。
7つのMIXのコツ
- ミックスの問題はミックスのせいではないかもしれない
- 位相問題は楽曲を台無しにする
- 「5クリックルール」を活用しよう
- 音圧戦争は終わっている
- ソロで聞くだけでは不十分
- 機材ではなく耳の問題
- ネットにあるアドバイスの99%は無意味
当サイトでは他にもミックスのコツについてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓