今回は英語版wikipediaの「ラグタイム」をまとめました。
この記事ではPart2として、ラグタイムで使われるコード進行や楽曲構成など、音楽的な特徴について解説していきます。
ラグタイムの音楽的特徴

ラグタイムは、John Philip Sousaによって作られたマーチを変化させたスタイルで、アフリカ音楽のポリリズムを取り入れています。
基本的には2/4や4/4で書かれており、1・3拍目に強拍を置いた左手のベースラインが特徴的です。
右手では、2・4拍目にシンコペーションを伴ったコードを弾きます。
ちなみに3/4拍子で書かれたラグタイムの曲は「ラグタイム・ワルツ」と呼ばれています。
ラグタイムには決まった拍子がない
「ワルツは3拍子」「マーチは2拍子」というように、ラグタイムは特定の拍子が決まっているわけではありません。
むしろ、ラグタイムの音楽スタイルはどんな拍子にも使えるようになっています。
ラグタイムでは「シンコペーション」がよく使われる

ラグタイムの大きな特徴の一つとして、「拍節の間にメロディーのアクセントを入れるシンコペーション」があります。
例えばメトロノームを鳴らして演奏したときに、メトロノームと被らない位置で(メトロノームが鳴る少し前に)メロディーにアクセントが来ることが多いです。
まるで、メロディーが伴奏が弾いている拍を避けているように聞かせることができます。
例えば、ラグタイムで最も有名な楽曲の1つ「The Entertainer」の楽譜を見てみましょう。
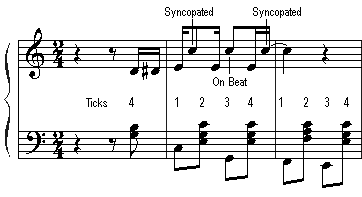
画像:ラグタイム「The Entertainer」の譜面例(https://www.perfessorbill.com/misc/ex02.gif))
シンコペーションを使うととてもリズミカルに聞こえるので、よりノリやすくなります。
ちなみにシンコペーションについてはこちらの記事で詳しく解説しています↓
ラグタイムでは「スイング」がよく使われる

ラグタイムにおける著名な作曲家・ピアニストのScott Joplinは、ラグタイムの音楽スタイルに関して「”スイング”を掴むまで、ゆっくり演奏する」と発言しています。
この「スイング」という名前は、のちにラグタイムから発展したジャズに使われることとなります。
ラグタイムではない音楽をラグタイムにするには、メロディーの時間値(長さ)を変えて「ラギング(ラグする)」させることにより実現できます。
ラグタイムの楽曲の構成

ラグタイムの楽曲ではいくつかの「テーマ」を使うことが基本で、多くは4つのテーマを用いて作曲されます。
各テーマは16小節分あり、それぞれのテーマは4小節x4のフレーズに分けられています。
主なパターンはこちらの3つです。
AABBACCC
AABBACCDD
AABBCCA
場合によっては、4~24小節の間、テーマとテーマの合間に4小節のイントロかブリッジが使われることもあります。
ラグタイムのコード進行

ラグタイムでよく使われるコード進行として、セカンダリードミナントを使った「ラグタイムプログレッション」があります。
これはセカンダリードミナントをひたすら繋げていく、つまり五度圏(サークルオブフィフス)に従ってコードを繋げていく奏法です。
ディグリーネームで表すと..
たとえばCメジャーキーなら、このようになります。
E7 - A7 - D7 - G7 - C
ラグタイムでは「ストライドピアノ」がよく使われる
ラグタイムは、ストライドピアノのルーツも持っています。
これは1920年代から1930年代に人気となったスタイルで、より即興的なピアノスタイルが特徴です。
ラグタイムでは、このストライドピアノも多く使われています。
つづき「ラグタイムの歴史」↓











