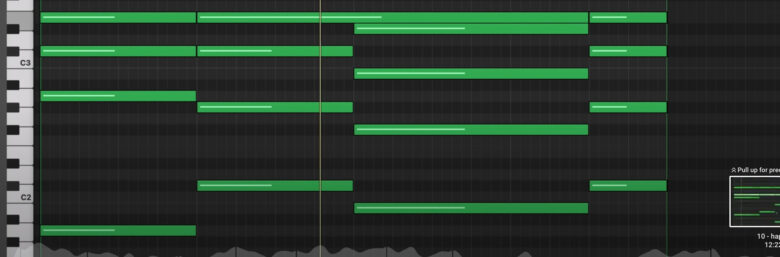今回は、Justin Collettiが解説する「あなたのミックスは本当にマスタリングの準備ができていますか?」をまとめました。
ミキシングエンジニア・マスタリングエンジニアとして活躍しているJustinが、長年の経験からわかった「マスタリング前までにミックスでやっておくべきこと」を2つ教えます。
完璧なミックス(MIX)をするためのコツ2つ

マスタリングの準備ができている「完璧なミックス(MIX)」をするためのコツは、こちらの2つです。
- 自分が持っている力をすべて発揮すること
- フィードバックをもらうこと
それでは1つずつ解説します。
完璧なミックス(MIX)をするためのコツ1つ目

完璧なミックス(MIX)をするためのコツ1つ目は「自分が持っている力をすべて発揮すること」です。
「キレイに聞こえるかどうか」「大きく聞こえるかどうか」ではなく「自分でできることを最大限やっているかどうか」が一番大切です。
僕はマスタリングエンジニアとして仕事をしていますが、ミックスに何か問題があると感じたときは、ミックスをした人の「技術的な問題」ではなく「美学的な問題」が原因であることが多いです。
つまり「どんなミックスにしたいのか」「理想のミックスのために自分がするべきことは何か」がよくわかっていないままミックスをしているのです。
ミックスやマスタリングにおける「技術的な問題」の例

例えばステレオのオーディオファイルをマスタリングエンジニアに渡さなければないのに、モノラルで送ってしまったら、それは致命的かつ技術的な問題です。
しかし、それは「音がモノラルになってしまっているので、ステレオに直していただけますか?」と言えば解決する話です。
また、wavファイルではなくmp3ファイルで送ってしまった場合も同様です。
「よりよい品質のために、wavファイルでお送りいただけますか?」とお願いして、送り直してもらえれば解決します。
ミックスやマスタリングにおける「美学的な問題」の例

それでは、技術的な問題ではなく「美学的な問題」にはどのようなものがあるでしょうか?
これには、周波数帯域や音の聞こえ方、ツールの使い方や選択に関する問題などが挙げられます。
「60Hz付近の低音域が多すぎる」「リミッターをかけすぎている」などです。
しかし、これらは一概に「問題」とも言えません。
60Hz付近がたくさん鳴っている曲はありますし、リミッターをかけすぎている音が欲しいときもあります。
つまり「出過ぎているからダメ」「使い過ぎているから問題」なのではなく、その人がそれを正解だと自信を持って言えない状態であること、どんな曲を作りたいのかをしっかり考えられていないことが問題です。
これが美学的な問題であり、その人にとっての美学=理想の音楽がきちんと定まっていないことが問題です。
完璧なミックス(MIX)をするためのコツ2つ目

完璧なミックス(MIX)をするためのコツ2つ目は「フィードバックをもらう」です。
自分の曲だと何回も聴き過ぎているので、正確な判断ができなくて困っています。一度聞いてフィードバックをもらえませんか?
このような質問をいただくことがあります。
このときに大切なのは「第三者にフィードバックをもらうこと」なのですが、できれば音楽の知識・技術がある人と直接話しながらフィードバックをもらうことをおすすめします。
マスタリングエンジニアだけでなく、ミキシングエンジニア、音楽プロデューサーなどに聞いてもよいでしょう。
直接フィードバックをもらうことはなぜ大切?

僕は5分間の曲を1回聴いただけで、30個ぐらいのアイデアや修正案が思いつきます。
そのため、真面目にフィードバックをしようとすると「ここはこうすることもできるし、こうすることもできますかどうしますか?」「これをやると、こういうメリットもありますがこのようなデメリットもあります」などかなりの長文になってしまいます。
もしこの長文のフィードバックをメールで送るとしたら、その文章を読んだだけでこちらの説明をクライアントが完璧に理解できるとは限りません。
そのため、僕は「コーチングコール」というサービスを提供し、通話でクライアントにフィードバックをするようにしています。
マスタリングにかかるお金よりも高額にはなりますが、しっかり時間を作ってクライアントに向き合い、リアルタイムでお話しながら実例もその場で紹介できます。
何よりも僕はこれがとても好きなので、通常の予約を受け付けるときよりも1時間あたりの金額を安く設定しています。
1曲に対して1時間じっくりフィードバックをすることもあれば、1時間で3~4曲分のフィードバックをすることもあります。
いずれも、クライアントのみなさんにご満足いただいています。
「魚を売るな、魚の捕り方を教えろ」

クライアントの中には、僕をとても信頼してくれて、何度も何度もコーチングコールを利用してくれる人もいます。
そんな人たちが、あるときからこのサービスを利用しなくなると、僕はとても嬉しくなります。
僕がそれまでにお送りしてきたフィードバックのおかげで、その人たちのミックスのスキルが上がった証拠だからです。
まさに「魚を売るな、魚の捕り方を教えろ」です。
教える仕事の醍醐味だと思いますし、こんなに素晴らしい仕事はないと思います。
10曲作ったら2曲分のフィードバックだけもらおう

フィードバックをもらうときにもう1つお伝えしたいのが、たくさん曲を作ってもフィードバックをもらうのは2曲程度にしておくということです。
例えば10曲収録されたアルバムを作っているとき、10曲全部聴いてもらうのではなく、まずは1~2曲分だけ聴いてもらいましょう。
フィードバックをあげる側の負担も減りますし、自分で考えて修正する力も身に付きます。
例えば僕のクライアントでは、「9曲入りのアルバムのミックスが終わったのでフィードバックが欲しい」と相談してくれた人がいました。
その人には「そのうちの2曲だけ送ってください」と伝え、はじめに2曲分のフィードバックを送りました。
すると、その2曲分のフィードバックをもとに9曲すべてに修正を加えてくれたのです。
中には「Ver.30」まで到達していた楽曲もあり、彼がフィードバックをもらってからどれだけ試行錯誤してくれたのかが伝わります。
このように、ほんの少しのヒントであっても他の楽曲に応用することもできます。
そのため「10曲作ったら2曲分のフィードバックだけもらう」を実践すると、ミックスのスキルが上がりやすくなります。
よくある質問「自分はちゃんとミックスできていますか?」

マスタリングエンジニアをしていると、ミキシングエンジニアなどミックスを担当した人から次のような質問や相談のメッセージを頂きます。
マスタリングをしてもいいぐらい、自分はちゃんとミックスできていますか?
正直なところ、僕はマスタリングをする前にこの質問に答えることはできません。
マスタリングをやってみないと、ミックスの問題点はわからないからです。
マスタリングをやってみないとミックスの問題点がわからない理由

マスタリングエンジニアはマスタリングをする音源ファイルを受け取った後、イスに座って30分かそれ以上じっと耳を澄ませて音を聞き、問題がないかをチェックします。
そしてEQやリミッターなどのツールを使いながら、何をすれば明るい音になるか、何を使えばバランスのいい音になるかなどを確認します。
つまり、マスタリングをやってみてはじめてその曲の問題点を洗い出すことができるのです。
そのため、僕は「ミックスはちゃんとできていますか?」と聞かれたら、まずはマスタリングをやってみて、マスタリングの工程で行ったことを1つずつメモして渡しています。
もちろん、一度聞いて直感で「うーん、なんだかバスドラムがちょっと大きすぎる気がするな」などと感じることはあります。
しかし、具体的にバスドラムの何が原因で大きすぎて聞こえるのか、他の楽器の何がバスドラムが大きく聞かせているのかはわかりません。
そのため、マスタリングの工程で行うようなEQの微調整などをやってみないと、ミックスのフィードバックはできないのです。
マスタリングエンジニアとして僕が心がけていること

僕はマスタリングエンジニアとして、「ミックスの問題点は、マスタリングをしてみてからでないとわからない」ということを知っています。
そのため、クライアントにマスタリングを頼まれたり質問・相談をされたら、無償でフィードバックをし、再マスタリングも行っています。
まずはクライアントからマスタリングする音源ファイル(2mix)をもらい、それをマスタリングします。
もしマスタリングのときに問題点を見つけたら、「問題点は何か」「その問題点を解決した方法」を添えてクライアントに渡します。
クライアントはそれをもとに再度ミックスを調整し、新しいバージョンの音源ファイルを送ってくれるので、僕はそれをマスタリングして完了となります。
はじめに異なる2バージョンの音源ファイルを送ってもらった場合は、それぞれにフィードバックをお送りすることもしています。
一流のアナログ音楽スタジオでは再マスタリングが難しい理由

超一流のマスタリングエンジニアは、素晴らしいアナログ機材を数多く取り揃えたスタジオでマスタリングをすることがあります。
このようなマスタリングエンジニアの場合は、僕のように無償で再マスタリングをすることはかなり難しいと思います。
アナログ機材を多数使っていると、設定を復元するのに時間がかかってしまうからです。
アナログ機材は1つ1つのツマミの位置(向き)などを調整して使うので、「この曲ではEQの高音域のツマミは1時の向きで、コンプレッサーのアタックは10時の向きで…」などをすべて復元するのに時間がかかります。
そのため、同じように設定したつもりでも、やはり人間ですから、若干音が違っていたりもします。
一方、DAWのプラグインのみを使っている場合やアナログ機材を少ししか使っていない場合は、DAWのプロジェクトファイルを開き、アナログ機材を少し調整するだけで設定を復元できます。
そのため「前のバージョンより少し高音域を増やした音源をください」と言われても、すぐにお送りすることができます。
AIマスタリングにはできないこととは?
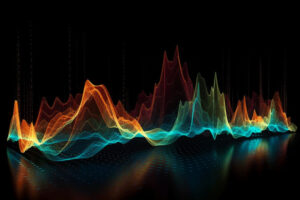
最近では、1曲数百円〜1000円程度でマスタリングをしてくれる「AIマスタリングサービス」も誕生しています。
マスタリングエンジニアはそのようなサービスと戦っていかなくてはいけない時代になりました。
しかし、AIはクライアントと具体的な会話や相談ができません。
長年経験を積んだマスタリングエンジニアであれば、これまで手がけてきた作品や聞いてきたヒット曲のデータが頭に入っているので、クライアントの理想と自分の知見をもとに細かく設定を調節することができます。
その人に合ったマスタリングをするための会話やフィードバックができるので、これはAIには負けないポイントだと思います。
余談ですが、AIマスタリングサービスを使うと「より大きく聞こえても、より悪く聞こえるようになる」と個人的には感じています。
以上が「マスタリングエンジニアが教える完璧なミックス(MIX)をするためのコツ2つ」でした。
当サイトでは他にもミックスのコツをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください。