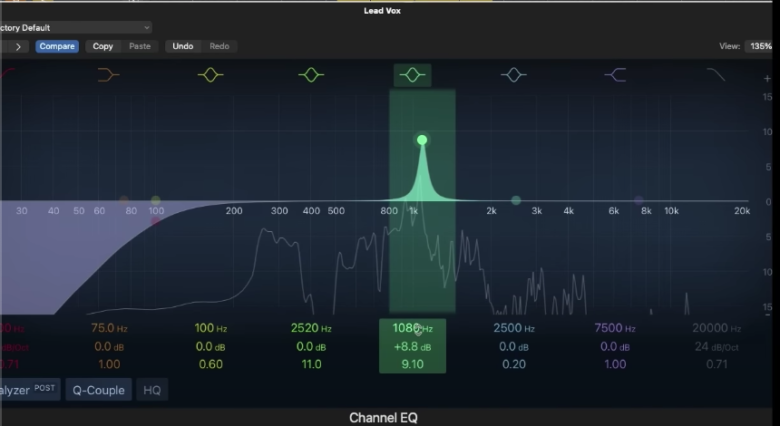ミックス(MIX)の効率を上げたい!
もっと上手にミキシングができるようになりたいけど、どうすればいいの?
今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。
ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanが教えるミキシングの効率をアップさせる21のコツをまとめました。
今回はPart2として、4~6個目のコツをご紹介します。
ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanによるミックスのコツシリーズ
どれも今から実践できる内容ですので、ぜひお試しください!
ミックスのコツ4:リファレンストラック(参考曲)を使おう

ネットでミキシングについて検索すると「リファレンストラック」という言葉をよく目にすると思います。
この「リファレンストラック」とは、「プロの手によってミックス・リリースされている+自分が今ミックスしている曲と似ている曲」のことを言います。
たとえばロックの曲をミックスしているなら、自分が最もインスピレーションを受けたロックの楽曲や、似た編成・スタイル・音のロックの曲をリファレンスとして選びます。
どこでも通用するミックスにできる
このリファレンストラックを参考にしながらミキシングすることは、非常に重要です。
なぜなら、プロがミックスした曲は、どんな音楽環境で聞いてもよく聞こえるミキシングになっているからです。
音楽制作用のモニタースピーカーはもちろん、スマホのスピーカー、カーステレオ(車)、音質がひどいBluetoothスピーカーなどで聞いてもしっかり聞こえるようにミックスされています。
つまり、このようなプロがミックスした曲のようにミックスできれば、あなたの曲も「どこで聞いてもよく聞こえる曲」になるのです。
ミックスのコツ5:シリアルコンプレッションを使おう

ミキシングにおいては「ボリュームのバランスを取る」「EQの使い方」「コンプレッサーの使い方」の3つは大きなキーポイントとなります。
しかしコンプレッサーにおいては、多くの人がゲインリダクションを多く取りすぎるほど強くコンプレッションをしています。
つまり、「音は潰せるだけ潰そうとして非常に強くコンプレッサーを使っている」ということです。
このような使い方をすると、音が潰れているように聞こえたり、音が歪んだり、いかにも「デジタル」な感じの音になったりと、音が非常に不自然になります。
では、音量を適度にコントロールしつつ、音を自然に聞かせるにはどうしたらいいのでしょうか?
シリアルコンプレッションを使おう
ここでおすすめするのが「シリアルコンプレッション」です。
シリアルコンプレッションとは、2~3つのコンプレッサーを重ねて使い、それぞれ薄くコンプレッサーをかけていくことです。
つまり、1つのコンプレッサーを使って一気に9dBSのコンプレッションをかけるのではなく、3つのコンプレッサーを使って、それぞれ3dBSずつのコンプレッションをかけるのです。
同じ10dBSのコンプレッションでも、1つのコンプレッサーで行うコンプレッションの量が少ないので、より自然な音でコンプレッションできるのです。
ちなみに、それぞれのコンプのAttack TimeやRelease Timeを変えてみると、より柔軟にコンプレッションすることができます。
たとえば1つ目のコンプでは、「トランジェント調整用」として、速めのAttackとReleaseに設定。
2つ目と3つ目のコンプは、「トーン調整用」として、中ぐらいのAttackとReleaseに設定するなどの工夫ができます。
ミックスのコツ6:ボリュームバランスに目を向けよう

ミックスにおいてボリュームバランスを取ることは最も重要なので、これに一番時間を時間をかけてOKdす。
ボリュームバランスを取るときにおすすめなのが、ハイトオーダー(Hight Order)を使う方法です。
ハイトオーダーとは?
ハイトオーダー(Hight Order)とは、曲の中で最も音量が大きい部分をループ再生したとき、最も重要なパート以外の音量を全て下げるという方法です。
この「最も重要なパート」というのは、ボーカルかもしれないし、キックかもしれないし、スネアかもしれません。
これは曲によって異なります。
いずれにしても、この最も重要なパートは-5dBに設定しておきましょう。
この状態で他すべてのパートの音量を下げると、重要なパートだけがスポットライトを浴びたように目立つことができます。
Part3はコチラ↓
ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanによるミックスのコツシリーズ