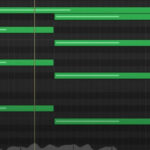洋楽でよく使われているコード進行が知りたい!
洋楽っぽい曲が作れない…
このようなお悩みにお答えする内容です。
オンラインでピアノレッスンを開講しているPianoPigが解説する「”4コード"を学ぼう」をまとめました。
この「4コード」を覚えるだけで、何百もの楽曲が弾けるようになります!
それだけたくさんの楽曲で使われているコード進行ですので、ぜひこの機会にマスターしてみてください。
4コードとは?

4コードとは、この4つのコードで構成されるコード進行のことです。
I - V - vi - IV
Cメジャーキーなら、こうなります。
C - G - Am - F
とてもシンプルです。
4コード(I-V-vi-IV)を使っているヒット曲の例
キーやリズムパターンはそれぞれ異なりますが、同じ4コード(I-V-vi-IV)を使っているヒット曲は非常にたくさんあります。
バリエーションの変え方
それでは、ここからはこの4コードを使って、バリエーションを増やす方法をご紹介します。
今回ご紹介するのは、こちらの4つです。
- 転回形を使う
- ルート音(ベース音)を変える
- リズムを変える
- オリジナルのリズムを作る
転回形を使う
4コードは、転回形を使うとさらにバリエーション豊かになります。
たとえばCメジャーコードは「C E G」という並びですが、このような順番で鳴らすと、また違った響きになります。
E G C(第一転回形)
G C E(第二転回形)
ルート音(ベース音)を変える
また、ルート音を変えても違った響きにさせることができます。
たとえばCメジャーコードの場合。
通常のルート音はCですが、これをEやGにしてみましょう。
ピアノだと、左手でルート音(EやG)を弾き、右手でC・E・Gを弾くイメージです。
これだけでも、また違った響きにさせることができます。
リズムを変える
ここからは、コードを鳴らす楽器のリズムを変えてバリエーションを増やす方法をご紹介します。
「スプリットコード」を使う
「スプリットコード」とは、文字通りコードをスプリット(分割)する方法です。
たとえばCメジャーコードの場合。
コードの構成音はC・E・Gですが、これを一気に鳴らすのではなく、このように鳴らしてみます。
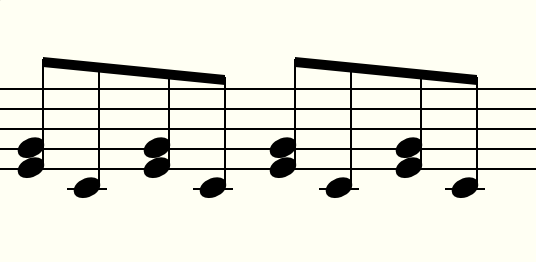
※EとG→C→EとG→C
アルペジオを使う
「スプリットコード」は「分割」でしたが、コード音をすべてバラバラにする「アルペジオ」も使えます。
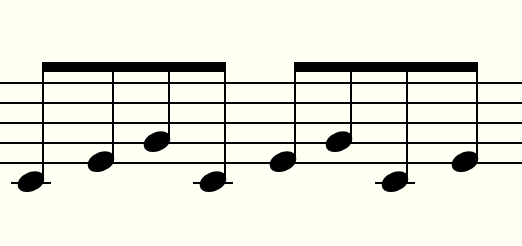
オリジナルのリズムを作る
今回はスプリットコードとアルペジオをご紹介しましたが、他にもさまざまなパターンを作ることができます。
自分が思いついたステキなリズムを作ってみましょう。
まとめ
今回は、4コードの定義から使い方までたっぷりご紹介しました。
このコード進行を覚えたら、あとは好きなキーに変えてメロディーをつけるだけで曲ができちゃいます。
非常に便利なコード進行ですので、ぜひおためしください!
当サイトでは他にもコード進行についての解説をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓