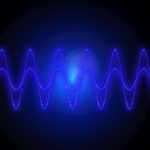今回は「サンプリングレートが変わると、なぜ音程(ピッチ)が変わるの?」というご質問にお答えします。
「48khzで録音した音源を96khzのDAWプロジェクトにインポートしたら、なんか音が変わってた…」ということはありませんか?
今はDAWがこの問題に対応してくれることもあり、このトピックに関してあまり考えたことのない人もいるかもしれません。
しかしこの問題や原理を知っておかないと、のちのち大問題になることもあります。
この記事ではパラパラ漫画に例えてわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
「48khzのオーディオ」って、どういうこと?
「サンプリングレート48kHzのオーディオ」というのは、「1秒間に48000回サンプリングされている音源」ということを表します。
かんたんに言うと、1秒間に48000個の情報が入っているオーディオファイルということです。
プロジェクトのサンプリングレートとオーディオのサンプリングレートが違うとどうなる?
プロジェクトのサンプリングレートとオーディオのサンプリングレートが違うと、ピッチ・再生速度が変わります。
ここからは、以下2つのパターンにおいて、どのような変化が起きるのかを解説していきます。
プロジェクトのサンプリングレートよりもオーディオのサンプリングレートの方が小さいとき
オーディオのサンプリングレートよりもプロジェクトのサンプリングレートの方が小さいとき
サンプリングレートが96khzのプロジェクトに、48khzのオーディオを入れたらどうなる?
プロジェクトのサンプリングレートがオーディオのサンプリングレートの2倍の場合、サンプル(情報)が2倍の量に複製されます。
たとえば、プロジェクトのサンプリングレートが96khz、オーディオのサンプリングレートが48khzのとき。
プロジェクトのサンプリングレートの数字(96)に合わせるには、オーディオが2倍(48x2)の情報量がないと追いつきません。
そのため、1秒間に48000個の情報があったものを、無理やり96000個に増やしているのです。
振幅数が増えると、音が高くなる

画像引用: http://www.mb.ccnw.ne.jp/kontoshi/papa/gimon/oto.htm
小学校の理科の授業で、「1秒あたりの振幅数が増えると音が高くなる」という原理を学んだことを覚えているでしょうか?
実ははこれと同じです。
本来は1秒あたり48000の情報量だったのに、2倍の情報量=振幅数になるため、音が高くなるのです。
プロジェクトのサンプリングレートが、オーディオのサンプリングレートの1/2だったらどうなる?
この場合は、1秒あたりのサンプル量が1/2になります。
パラパラマンガにたとえてみると...
たとえば1秒に60枚の紙を使って、人間が走っているパラパラマンガを作ったとしましょう。
ここでもし「1秒間に30枚の紙しか使っちゃダメです」と言われたら?
この場合は、1/2のスピードで紙をめくっていくことになります。
つまり、1秒60枚で作ったマンガを、2秒で60枚のスピードで流します。
1秒60枚でぴったりのスピードだったのに、遅いスピードで再生しなければいけなくなりました。
人間が走っているマンガだったのに、これだと歩いているぐらいのスピードになってしまいます。
それでは、もし「1秒間に120枚の紙を使ってください」と言われたら?
もともと60枚の紙しか使っていないので、とりあえず今持っているページを何枚もコピーして、120枚に増やさなければいけません。
そして、1秒60枚で作ったマンガを1秒で120枚のスピードで流していくことになります。
言い換えると、本来に比べて2倍のスピードで紙をめくっていくことになります。
1秒60枚でぴったりのスピードだったのに、ものすごいスピードで走る人間のアニメーションになってしまいます。
紙:サンプル
1枚あたりの枚数:サンプリングレート
この例でいう「紙」がサンプル(情報)で、「1秒あたり何枚」がサンプリングレートです。
パラパラマンガはアニメーションが遅くなるという結果になりますが、オーディオの場合は音が低くなります。
なんとなくイメージがついたでしょうか?
サンプリングレートが変わると、なぜピッチが変わるの?まとめ
今回の内容をざっくりまとめると、このようになります。
プロジェクトのサンプリングレートが、オーディオのサンプリングレートの2倍のとき
サンプル量が2倍 = 2倍のスピードで再生される = 音が高くなる
プロジェクトのサンプリングレートが、オーディオのサンプリングレートの1/2のとき
サンプル数が1/2 = 1/2のスピードで再生される = 音が低くなる
これを覚えておくと、レコーディングやオーディオ素材を扱うときに役立ちます。
今はDAW側でサンプリングレートを手軽に変換できるようになっていますが、これを覚えておけば後々レコーディングやオーディオ素材を扱うときに困ることはないでしょう。
ぜひ頭の片隅に置いておいてください。
当サイトでは他にもDTM・オーディオ用語についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓