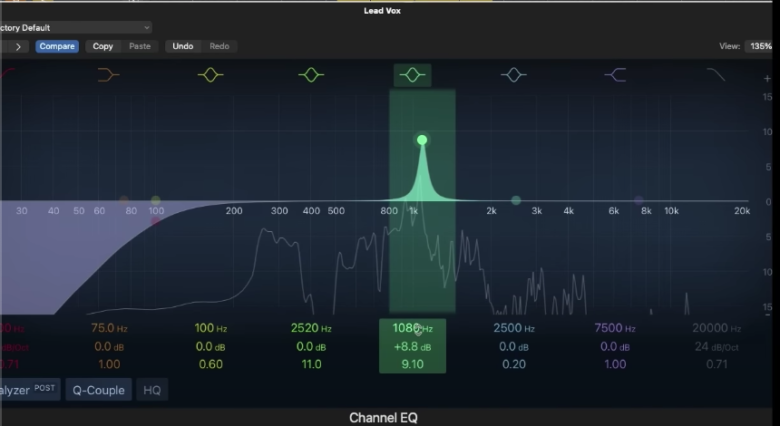今回はこのような方向けの内容です。
この記事を読めば、今後どんなコンプレッサーを見ても「あぁ、あのタイプね」「こういう音が欲しいから、この種類のコンプレッサーを使おう」と、使いどきがわかるようになります。
コンプレッサーの種類1. Platinum Digital

Platinum Digitalは、Logicの中でもごく普通のコンプレッサーです。
コンプレッションはよく効きますが、音楽的なコンプレッションにはなりません。
デフォルトの設定はこのようにしておくと便利です。
Threshold:-30あたり
Knee:1.0
Attack:20ms
Release:100ms
コンプレッサーの種類2.Vintage Opto

Vintage Optoは、LA-2Aをモデルとした、Platinum Digitalよりもレスポンスが速いコンプレッサーです。

画像:LA-2A(https://media.uaudio.com/assetlibrary/t/e/teletronix_la2a_carousel_1_1.jpg)
音はよりソフトで音楽的になり、音の鳴り方がよりよく強調されます。
ためしに、同じ設定でコンプのサーキットだけ変えた時に、どれほどレスポンスが速くなったかを聞いてみてください。
ディストーションも活用しよう
またVintageコンプでは、ぜひ「ディストーションモード」を試してみてください。
最初は「Soft」の設定にし、次にディストーションをかけてみると(Hardにする)、倍音のサチュレーションがかかったことがわかると思います。
コンプレッサーの種類3.Vintage FET

Vintage FETは、「Bluestripe 1176」をモデルにしたコンプです。

https://d2ijz6o5xay1xq.cloudfront.net/account_3142/urei-1176-blue-stripe-rev-b-front_4fde7e65721cc2306ea877d5429639cb_1000.jpg
LA-2Aをモデルにした「Vintage Opto」と比べ、もっとリアクションタイムが速くなっています。
Platinum Digitalよりもコンプレッションは音楽的になります。
コンプレッサーの種類4. Studio FET

Studio FETも「1176」をモデルにしたコンプで、同じく即効性のあるコンプレッションが特徴です。

https://musictech.com/wp-content/uploads/2016/11/bt1.png
Vintageモデルに比べて、少しだけサチュレーションが少ないです。
また、Studio FETはパラレルコンプレッションに最適のサーキットタイプです。
ドラムに使うと、少しだけ「ピシャッ」「バチンッ」と打ったような感じになります。
コンプレッサーの種類5.Studio VCA

VCAコンプは「Focusrite Red3」をモデルにした、「前に出ている感」が少ないことがよりはっきりわかるコンプです。

https://media.sweetwater.com/images/items/750/Red3-large.jpg?v=7e717edb688fcb3d
ためしに、耳を一旦リセットするためにVintage FETで音を聞き、次にStudio VCAにして聞いてみてください。
コンプレッサーの種類6.Vintage VCA

Vintage VCAはSSL Buss Compressorをモデルにしたもので、Kneeコントロールが加わったコンプです。

https://www.instrumentservicehuddinge.se/p/https-www-solidstatelogic-com-studio-gseries-compressor/
ドラムにかけたとき、このコンプがどれだけドラムの「一体感」を生み出しているかをチェックしてみてください。
特に小さい音で叩かれているときの音に注目です。
コンプレッサーの種類7. Classic VCA

Classic VCAは、dbx 160をモデルにしたコンプです。
ハードウェアと同様に、Classic VCAは「飾りのない」コンプです。
Vintage VCAのモデルにもなったSSLのように「まとまり」を作る効果はあるものの、操作はややわかりにくいです。
Kneeの可視化

ちなみにClassic VCAでは、コンプレッションの具合をビジュアルで確認することができるグラフがあります。
Input/Outputのグラフでは、信号レベルに対してどれだけコンプレッサーがかかったかを表示しています。
より高いRatioにしていると、ラインが大きく振れます。
Kneeはトランジション部分(推移している部分)で確認できます。
最後はMixの調整
ここまではコンプの特徴や設定について話してきましたが、設定の最後は「Mix」の値を調整していきましょう。
Mixの値を減らし、コンプレッサーをかけた音とかけていない音のバランスを取っていきます。
トランジェントをつぶすようなコンプレッションは、Mixレベルに応じて音にボディ(厚み)を与えます。
Logic Pro付属コンプレッサーの種類まとめ
今回はさまざまなスタイルやタイプのコンプレッサーについて解説してきましたが、それぞれを自分で比較しながら使ってみましょう。
たとえばドラムにコンプレッサーをかけたとき、どれも「コンプレッサーのかかったドラム」ですが、音楽的観点から見ると、それぞれ違いが出てきます。
これがコンプレッションの「アート」です。
さらに、コンプを組み合わせて使うことも可能ですので、ぜひためしてみてください。
この記事の前半「Opto・FET・VCA」の意味についてのまとめはコチラからご覧いただけます↓