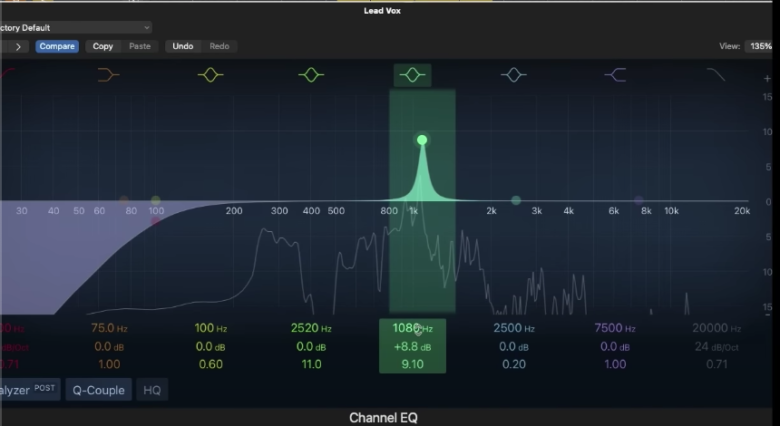DTMでボーカルにコンプレッサーをかけるとき、どんなことに気をつければいいの?
今回はこのような疑問にお答えする内容です。
DTMerおなじみ、サンプルやプラグインを販売するSpliceが解説する「ボーカルコンプレッションのやり方」をまとめました。
「ボーカルにはコンプレッサーをかけよう」とよく聞くと思いますが、なぜ使うべきなのか、どのように使えばいいかわからない方も多いでしょう。
この記事を読めば、今日からしっかり意図を持ってコンプを使えるようになります!
どんなときにボーカルにコンプレッサーをかければいいの?

コンプレッサーの主な役割は、「最も音が小さい時と大きい時の差をコントロールする」です。
最近の楽曲を聞くと、曲全体でボーカルの声が一定の音量で聞こえることがお分かりになると思います。
こういう時は、だいたいボーカルに対して強くコンプレッサーをかけており、ダイナミクスレンジ(抑揚の大きさ)が小さくなっているのです。
たとえば、Post Maloneの「Circles」という曲を聞いてみてください。
曲のどこから再生しても、ボーカルの音量に変化がないことがわかります。
コンプをかけてもかけなくても、いずれにせよみなさんはクリエイティブな方法を選ばなくてはなりません。
ここでの筆者のアドバイスは、「クラシックではない現代的な音楽ジャンルを作っているのであれば、コンプをかける」です。
だからといってかけすぎるのはよくないので、適度に使うのがベストです。
コンプレッサーを選ぼう

さて、コンプを使うときめたら、次は「どのコンプを使うか?」を決めることになります。
どのコンプレッサーも機能的には同じ効果が出ますが、それぞれが独自のキャラクターや質感を生み出します。
それでは、ここでボーカルに対してコンプを使った時、どのようなキャラ付けをされるのかをみてみましょう。
今回は、ArturiaのFX Collectionにあるコンプをいくつか使ってみます。
↓記事中にある音源「The original vocals」「The FET-76 (solid state) Compressor」「The VCA-65 (solid state) Compressor」「The Tube-STA (tube) Compressor」
ここで使われているボーカルは、ポップスやロックにぴったりのボーカルです。
それぞれの音を聞いてみると、筆者的にはFET-76が一番よいキャラですね。
VCA-65とTube-STAはちょっとなめらかすぎて、このタイプのジャンルにはエッジが足りない感じがします。
ざっくりまとめると、コンプはそれぞれ違ったサウンドになりますので、目的に合わせてコンプを使い分けられるようにするとようでしょう。
ボーカルコンプの設定のしかた

ボーカルコンプレッションにおいて、「絶対にこれがいい」という方法はありません。
しかし、ボーカルコンプをするにあたっていくつか覚えておいてほしい「キーとなるパラメータ」がありますので、そちらをご紹介します。
Ratio(レシオ)
一般的に、低いRatio(2:1や3:1など)はやさしくコンプをかけたい時によいと言われています。
すでに音量をよくコントロールできているボーカルに対して使うとよいでしょう。
高めのRatio(4:1やそれ以上)は、よりアグレッシブなサウンドに仕上げることができます。
非常に感情的で、声が大きくなったり小さくなったりなど、音量差が激しいときなどに使うとよいでしょう。
AttackとRelease(アタックとリリース)
エネルギッシュなラップボーカルなど、各フレーズの最初に重心を置く場合は、よりAttack Timeを遅くするとよいでしょう。
Attackの時間を設けることで(Attack Timeを遅くすることで)、ボーカルにおいて音量が小さい部分だけにコンプレッサーがかかることになります。
逆のパターンにしてもOKです。
フレーズの頭にすごく強調されているとき、強調されすぎるのを防ぐためにAttack Timeを早くしても大丈夫です。
Release Timeを遅くすると、ボーカルがなめらかに、一定に聞こえるようになります。
一方で、Release Timeを速くするとコンプレッサーが速く”リセット”され、よりアグレッシブなサウンドに仕上げることができます。
よりコンプレッサーの使い方・ミキシングのコツを学びたい方には、こちらの書籍がおすすめです!
ミキシング・マスタリングについて、かなり広く学べます。

-150x150.jpg)