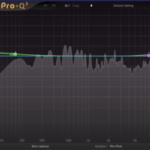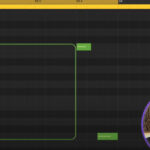今回は、音楽プロデューサー・オーディオエンジニアのJustin Collettiが解説する「音を大きく聞かせるための2つの秘密」をまとめました。
Justinは長年音楽業界でプロとして活躍しており、音楽プロデュース、ミキシングエンジニア、マスタリングエンジニア、音楽大学の講師など、幅広い分野で活躍しています。
そんな彼が、DTM・ミックスで音をより大きく迫力があるように聞かせる方法を2つご紹介します。
DTM・ミックスで音を大きく聞かせるのに最も重要なポイント

DTM・ミックスで音を大きく迫力あるように聞かせるのに最も重要なポイントは「コントラスト」です。
あらゆる「コントラスト」を工夫すると、音を大きく聞かせることができます。
ここからは、この「コントラストをつける方法」を3つご紹介します。
DTM・ミックスで音を大きく聞かせる方法1.同時に鳴らす音数を減らす

僕(Justin)は大学で音楽制作を学び、その後もプロとして仕事をしていますが、音がとても大きく迫力があるように聞こえる楽曲はどれも「楽器の数は少ないが、一つ一つの音が巨大に聞こえる」という点が共通していました。
「大きく聞こえる」と聞くと、「ギターが1本しかない」よりも「ギターが12本ある」というイメージが湧くかもしれません。
しかし、実際はギターが12本あるよりも1本しかない方が大きく聞こえることがあります。
さらに言えば、いろいろな音が一斉に鳴っているロックバンドの曲よりも、クラリネットが1本しか鳴っていない曲の方が大きく聞こえることがあります。
これは、1つの空間の中でその楽器が占める割合が異なるからです。
1枚の紙に絵を描くときの例
例えば同じ大きさの紙に「ボーカル・ギター・ベース・ドラム・ピアノ」の5つの楽器の絵を描くときと「クラリネット1本」の絵を描くときを比べてみましょう。

1枚の紙の中に5つの楽器を描くときは、他の楽器のスペースも空けなければなりません。
1つの楽器だけ大きく描くと他の楽器を描くスペースがなくなるので、1つ1つの楽器をある程度小さく描くか、楽器のどれかを大きく描く代わりに、他の楽器を小さく描いて妥協しなければいけません。
しかし、クラリネット1本しか描かないときはどうでしょうか?

他に描く楽器がないので、紙いっぱいに描くことができ、とても大きな楽器に見えます。
音楽も同じで、同時に描く絵の数=同時に鳴らす楽器の数が少ない方が、1つ1つの楽器の音が大きく聞こえるのです。
音数が少ないと1つ1つの楽器の存在感が大きくなる
先ほどの紙に楽器の絵を描くときもそうですが、楽器の数が少ないほど1つ1つの楽器の存在感も大きくなります。

例えば1枚の紙にクラリネット1本の絵を描くとき、そのクラリネットの絵を消してしまうと、紙は真っ白になってしまいます。
そのため、たった1本のクラリネットの存在感がとても大きくなります。

しかし、もし100本のクラリネットの絵を描いていたら、そのうちの1本を消してもそこまで大きな変化にはならないでしょう。
1本1本の存在感(面積)が小さいからです。
音楽でも同じで、鳴らす楽器の数を減らすと、1つ楽器が加わっただけで華やかに聞こえたり、1つ楽器が減っただけでとても静かに聞こえたりします。
逆に言えば、同時に鳴っている楽器の数が多ければ多いほど、1つ1つの存在感は小さくなり、音量も小さく聴こえます。
このように、1つ1つの楽器の存在感を大きくするためには、同時に鳴らす音の数を減らすことが大切です。
DTM・ミックスで音を大きく聞かせる方法2.セクションごとに音量を変える

例えばAメロとBメロが静かなとき、サビで音量を上げるとサビが爆発的に大きく聞こえます。
シンプルに「音量のコントラストがある」という状態です。
また、Cメロはハイカットフィルターを使ってラジオのように音をこもらせておき、次に来るサビでハイカットフィルターを外すと、サビがとても明るく華やかに聞こえるようになります。
この場合は「高音域の音量を変化させている」と言えます。
つまり、「Aメロ・Bメロ」と「サビ」で音量のコントラストをつけることで、より大きく聞こえるセクションが出来上がります。
なお、Aメロ・Bメロ・サビ・Cメロなど、セクションごとの作り方については下記の記事で詳しく解説しています。
それぞれのセクションの役割と作り方を理解すると、さらに楽曲を大きく迫力あるように聞かせることができますので、ぜひチェックしてください↓
背の高いバスケットボール選手が平均身長に見える理由
バスケットボール選手は背が高い選手がとても多く、2mを超える選手も少なくありません。
そんな背の高い選手たちが同じコートに集まると、彼らの背の高さを実感しにくくなります。
まるで、ごく一般的な平均身長であるかのように見えてしまうでしょう。

しかし平均的な身長の一般人の中にバスケットボール選手が混ざると、飛び抜けて大きく見えます。
バスケットボール選手が試合後にインタビュアーと横に並んだとき、はじめてその背の高さを実感した、ということはありませんか?
音楽もこれと同じで、同じぐらいの音量のセクションが何度も続いたり、同じぐらいの音量の楽器ばかり集めていると、その音量の大きさが目立たなくなり、存在感が薄れてしまいます。
音の長さを変えてスペースを作るのも重要

同じ1小節の中でも、音が大きく鳴っている拍と音が全くない拍があれば、音が大きく鳴っている拍のインパクトが強くなります。
そのため、音の長さを短くして前後に空白を作ると、音がより大きく聞こえやすくなります。
逆に、長く伸ばした方がズシンと重く大きく聞こえることもあります。
例えば同じ「1小節」でも、テンポ60の楽曲と120の楽曲では長さが2倍異なります。
テンポ60などのゆっくりな曲の方が、伸ばせる音の長さが長くなり、1音1音がずっしり重く聞こえやすくなります。
ミックスでは全部の音を大きく聞かせる必要はない

「音を大きく聞かせたい」と思ったとき、全ての音を大きく聞かせる必要はありません。
むしろ、すべての音を大きく聞かせようとした方が、すべての音が小さく聞こえてしまうことがあります。
これは前述のバスケットボール選手の例と同じで、音が大きく聞こえるかどうかは全体におけるバランス(他の要素との相対的な大きさ)で決まるからです。
そのため、ギターを大きく聞かせるためにドラムが小さくなってもいいですし、ドラムを大きく聞かせるためにギターが小さくなっても問題ありません。
セクションごとに大きく聞かせる要素を変えるのもOK

目立たせたい楽器をセクションごとに変更するのもいい方法です。
例えばイントロはドラムを大きく聞かせ、Aメロが始まったら新しく入ってきた他の楽器を目立たせるためにドラムの音量を下げる、というのもよいでしょう。
もしドラムが大きいままAメロに入ってしまうと、新しく入ってきたギターやボーカル、ベースが小さく聞こえてしまい「ドラムは大きく聞こえるけど、バンド全体だと小さく聞こえる」「すべての楽器が一斉に鳴っている割には小さく聞こえる」という印象になってしまうかもしれません。
オートメーションを活用しながら、本当に目立ってほしい音がしっかり目立つように調整しましょう。
「いいミックス=すべて大きく聞こえる」ではない

「いいミックス=すべてが大きく聞こえる曲」というわけではありません。
鳴らしている音がすべてはっきり聞こえるからいいミックスになるのではなく、必要な要素が大きく聞こえるからいいミックスになります。
そのため、「いいミックスだな」と思った楽曲があれば、ぜひ「何が大きくはっきり聞こえるか」だけではなく「何が大きく聞こえているとき、何が小さく聞こえているか」にも注意して聞いてみてください。
さらに一歩踏み込んで「何を大きく・小さく聞かせるとどんな気持ちになるのか」という音と感情のつながりにも注目してみてください。
以上が「音を大きく迫力を出して聞かせる3つの方法」でした。
当サイトでは他にも音を大きく聞かせるための方法をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓