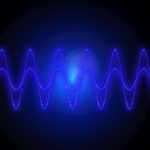プロ仕様のオーディオインターフェースと、安いオーディオインターフェースってどう違うの?共通点はある?
今回はこのような疑問にお答えする内容です。
プロドラマー・エンジニア・プロデューサーのEd Thorneが解説する「安いオーディオインターフェースvs高いインターフェースを比較してみた」をまとめました。
今回比較するのは、安くてコスパがいいと評判のFocusrite社「Scarlett 2i2」と、多くのプロが愛用するUniversal Audio社「Apollo Twin」です。
前者は20,000円程度、後者は15万円程度する製品ですが、一体何が違うのでしょうか?
また、共通点はあるのでしょうか?
こちらの記事を読むと、2つの違いだけでなくインターフェース選びの基準もわかってきますので、今後の機材選びの参考になります。
プロ仕様と最安のオーディオインターフェースの共通点
まずは、共通点から見てみましょう。
共通点1:ビット深度・サンプルレート
まず共通する音は、どちらも24bit・192kHzに対応していることです。
「24bit」などの「ビット深度」や「192kHz」などの「サンプルレート」についてよくわからない方は、こちらをご覧ください↓
共通点2:XLR・LINE Input
どちらもXLR・LINE Inputがあります。
共通点3:OS対応
WindowsとMac、どちらにも対応しています。
共通点4:+48Vファントム電源
+48Vファントム電源に対応しています。
(コンデンサーマイクを使う時などに使用します)
共通点5:ヘッドフォン接続
ヘッドフォンを挿して使える「ヘッドフォン接続」に対応しています。
Focusrite社「Scarlett」の魅力
さて次は、オーディオインターフェースごとに特徴を見ていきます。
まずは、Scarlettの魅力から。
こちらは、リーズナブルな上に必要な基本機能は十分備わっています。
また操作しやすい・見やすいデザインで、GAINのツマミはクリッピングしていると赤く光り、クリッピングしていない時は緑に光ります。
USB接続で動くのも魅力の一つです。
AIRモード
ちなみに「AIRモード」のボタンがありますが、これはプロの現場でも使われる「ISAプリアンプ」の音質をモデリングしているもの。
高音質で、レイテンシも少なく再生することができるモードです。
付属ソフトが多数
また、購入した時にPro Tools FirstやAbleton Live Liteなど、様々なプラグインやソフトが無料でついてきます。
買ったその日からこれらのソフトを支えるのは嬉しいですね。
Focusrite社「Scarlett」の懸念点
懸念点としては、モニターアウトプットが2つしかないことです。
ペアのスピーカーを1セットしか繋げないので、例えば複数のスピーカーを切り替えながら音楽制作をしたい人にはあまり向いていないかもしれません。
「Scarlett i4」などのハイグレードのバージョンだと値段は少し張りますが、モニターアウトプットが4つになるので、こちらを購入するとよいでしょう。
Universal Audio社「Apollo Twin」の魅力
次は、Apollo Twinについて詳しく見ていきましょう。
モニターアウトプットの数
Apollo Twinは、ステレオのアウトプットが2つ付いています。
つまり、ペアのスピーカーを2セット同時に繋げることができるのです。
どちらのスピーカーで聞くかをスイッチでかんたんに切り替えることもできます。
Monoモード
Monoモードのスイッチがあるので、Monoで聞いた時の状態もボタン一つで確認できます。
ミュートボタン
ミュートボタンもあるので、「音は出さずにレコーディングだけしたい」という場合にも便利ですね。
トークバック機能
別室(ボーカルブースなど)で演奏している人と会話するための「トークバック機能」も付いています。
ただし、多くの方は宅録で制作していると思いますので、こちらはさほど大きな影響はないかもしれません。
Apollo Twinは何でこんなに高いの?

では、なぜApollo Twinはこんなに高い値段なのでしょうか?
実はApollo Twinにはたくさんの機能やアイテムが付属していますので、特に魅力的なものをピックアップしてご紹介します。
プロレベルのプリアンプとEQ
まず、Apollo Twinを開発しているUniversal Audio社は、スタジオレベル(プロレベル)のプリアンプやEQを開発していることで有名な会社です。
有名なハードウェアには「Pultec EQ」などがあります。
(ちなみに解説者のEd Thorneは、これをいつもマスターバスに使っているそうです)
オフサイト コンピューターアクセス
また、「オフサイト コンピューターアクセス」も魅力の一つです。
これは、コンピューターのCPUに負荷をかけることなくUADのプラグインが使える機能です。
UADのハードウェアには「コンソール」と呼ばれるソフトウェアが付いてくるのですが、このソフトを使えば、CPUに負荷をかけることなくUADプラグインがリアルタイムで、レイテンシーなしで使えるのです。

画像:動画より
ADAT/SPDIF入出力
ADAT/SPDIF入出力が付いており、これを使うと他のUniversal Audio社の製品と接続することができます。
こうすることで、さらにパワフルなインターフェースへと強化することができるのです。
とりあえず最初に10万円ぐらいの一番小さなものを買っておいて、あとからよりパワフルな製品を買い足し、それらも同時に使うといった合わせ技が可能です。
UADのDAW「LUNA」が付属している

画像:動画より
Universal Audio社は、独自のDAW「LUNA」も開発しています。
DAWですので、Pro ToolsやLogic Proと同じようなものです。
まだ発表されてから日は浅いですが、ポテンシャルは高いです。
Apollo Twinを買えば無料で使えますし、付属の音源もたくさんあります。
ハイパス・シェルフィルター
次は、Apollo Twinに付いている各ボタンについての解説です。
まずはハイパス・シェルフィルター。
最初は75hzに設定されており、これを使うだけですぐ不要な低域をカットすることができます。
20dB パッドボタン
こちらはギターやキーボードなどで急に大きい音(信号)が発生した時に、音量を20dB下げる機能です。
Phaseボタン
ボタンを押すだけで位相を反転できます。
LINKボタン
ステレオマイクとリンクさせるボタンです。
Hi-Z入力
ギターやベースなど、ハイインピーダンスの楽器接続のためのインプットです。
付属プラグインが多い
先ほども少し触れましたが、Apollo TwinにはハイレベルなUADプラグインがたくさん付属しています。
特に、ボーカルやギターを宅録したい時にはものすごく便利です。
バラで買うと1つ1つが高いのですが、インターフェースなら付属してきますので、かなりお得でしょう。
ファンがない
内部に冷却用のファンが付いていないので、「宅録するときにインターフェースのファンの音がうるさい」という心配がありません。
ただし本体は熱くなるので、他のハードウェアとは少し距離をあけて置くのがよいでしょう。
Universal Audio社「Apollo Twin」の懸念点
ScarlettはAtoC USBアダプタが付属しています。
つまり、買ったその日にパソコンと繋げて使えます。
対してApollo Twinには、実はケーブルが付いていません…
そのため、自分でケーブルを用意しないと使えません。
高い・安いオーディオインターフェースの音質の違いは?
レコーディングした時の音質の違いは、もちろんあります。
Scarlettは値段に対して録れている音が非常によく、十分よいのですが、Apollo Twinの方がよりスムーズで空気感があり、はっきりと録れている印象があります。
Apolloはかなり細かいニュアンスまで拾えています。
以上がScarlettとApollo Twinの比較でした!
やはり値段の張るインターフェースは、それなりに良い機能が備わっていることがお分かりいただけたかと思います。
しかし、Scarlettのように1~2万円で買えるインターフェースもコスパは非常によく、特に初心者の方には十分すぎるクオリティです。
ぜひ今後のインターフェース選びの参考にしてください。
DTMにおすすめのオーディオインターフェース
DTMにおすすめのオーディオインターフェースは、価格別にこちらに掲載します↓
【初心者向け】2万円以内でおすすめのオーディオインターフェース
【中級者向け】2万円~5万円代でおすすめのオーディオインターフェース
【中級者〜上級者向け】6万円以上でおすすめのオーディオインターフェース
上記「Apollo Twin X」の魅力と「DUOとQUADの違い」についてはこちらの記事で解説しています↓