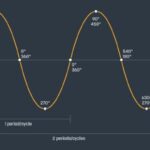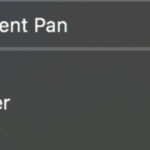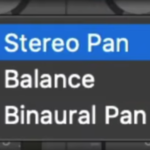今回は「プリフェーダーとポストフェーダーの違い」をまとめました。
DTMでリバーブを使うときは、「インサートとセンド」そして「プリフェーダーとポストフェーダー」の使い分けが大切です。
この記事ではこの2つのポイントについて、メリットとデメリットをそれぞれ解説していきます。
リバーブはインサート or センドのどちらを使うべき?

まずはじめに、インサートとセンドについて解説します。
リバーブなどのエフェクトを使うときによく考えるべきなのが、インサートとセンドの使い分けです。
インサート(Insert)
エフェクトをかけたいトラックに、エフェクトプラグインを直接追加する方法
センド(Send)
エフェクト専用のトラックを別途作成し、そのトラックに音を送ってエフェクトをかける方法
一般的に、リバーブやディレイなどのエフェクトではセンドがよく使われます。
センドのメリット
・複数のトラックに対して同じエフェクトがかけられる
(どの楽器も同じ空間にいるように聴かせることができ、まとまりが出る)
・CPU負荷を減らせる
(同じプラグインを何個も作成する必要がないため)
プリフェーダーとポストフェーダーとは?
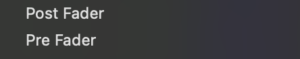
次は、プリフェーダーとポストフェーダーについて解説します。
この2つは「音量フェーダーを通る前にエフェクトをかけるのかどうか」が異なります。
プリフェーダー
音量フェーダーを通る前にエフェクトをかける
ポストフェーダー
音量フェーダーを通った後にエフェクトをかける
例えばボーカルにリバーブを使うとき、プリフェーダーの場合は「ボーカル→リバーブエフェクト→音量フェーダー」の順で音が通ります。
ポストフェーダーの場合は「ボーカル→音量フェーダー→リバーブエフェクト」の順です。
つまり、プリフェーダーにすると音量フェーダーによってリバーブの量が変わることがなく、常に一定の量でリバーブが加わります。
ポストフェーダーにすると、音量フェーダーが上がればリバーブの量も増えます。
インサートはプリフェーダー、センドはポストフェーダーがデフォルト

基本的には「元の音が大きくなればリバーブの量が増える」という聞こえ方の方が自然なので、多くの場合はセンドをポストフェーダーの設定にしてリバーブをかけます。
実際に、多くのDAWはセンドエフェクトのデフォルトがポストフェーダーになっています。
一方、インサートでエフェクトを追加している場合はプリフェーダーがデフォルトになっています。
つまり、多くのDAWでは以下の順番がデフォルトになっています。
元の音→インサートエフェクト→プリフェーダーのセンドエフェクト→音量フェーダー→ポストフェーダーのセンドエフェクト
プリフェーダーとポストフェーダーの違いまとめ
以上が「プリフェーダーとポストフェーダーの違い」の解説でした。
プリフェーダー
音量フェーダーを通る前にエフェクトをかける
エフェクトの量が音量フェーダーによって左右されない
ポストフェーダー
音量フェーダーを通った後にエフェクトをかける
エフェクトの量が音量フェーダーによって左右される
音の信号が流れる順番
元の音→インサートエフェクト→プリフェーダーのセンドエフェクト→音量フェーダー→ポストフェーダーのセンドエフェクト
当サイトでは他にもDTMのパラメーターや操作について解説していますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻
参考:https://www.youtube.com/watch?v=wK9bfwJl4cg